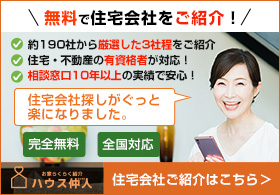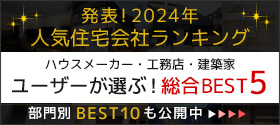住宅関連記事・ノウハウ
 「家相」は新しい家を創れるか?
「家相」は新しい家を創れるか?
何度か「家相」についてお話をし、今回も親たちや周りの“鬼門信仰?”から経済封鎖に陥ったり、私自身が自信を無くした時の家相のエピソードなどの体験もお話しして、独自の統計で若年層にまで浸透していることなどでまさしく家づくりの精神的文化ともなっているようとも思えるのです。
1 「鬼門」の影響力が家相?

写真:京都町家:長江家正面(写真:筆者)
誰もが鬼門の存在が気になるものです。親しい周りから責められれば、さらに大きな“鬼門”となり、「家相は存在する」と誰もが気にするのです。
筆者自身がこの家相を意識することは生家に由来するのかも知れません。それはゆうに100年を越す家で、幸いに空襲から免れ、その家で育つことができました。南入りの広い玄関は三和土(たたき)の土間*で、玄関の右脇に大きな洞穴があり、そこにもみ殻に包まれたサツマイモやジャガイモなどが保管されていました。

写真:同上:長江家正面土間三和土(たたき)の土間京左が店(写真:筆者)
上がった上がり框(かまち)は店と呼ばれる8畳ほどの畳の間が縁をはさんであり、その右角に黒光りする一尺角ほどの大黒柱が悠然と立っていました。土間は裏の勝手へとつながり竃(くど=へっつい)があり、そこで薪が燃され釜が煮立っていました。その湯気も薪の煙も皆屋根裏に吸い込まれて梁(はり)や母屋(もや=屋根を構成する木組み)も煤(すす)で真っ黒になって、果てしない宇宙のような感じさえしたものです。
その土間で暮れ頃は糯米(もちごめ)を蒸籠(せいろ)で蒸して、石臼で搗(つ)いて正月の支度をしたことを今も不思議に、もうもうと立ち上がる真っ白な湯気とその匂いが、まるで昨日のことのように思い出されるのです。竃や土間、流しや神棚をいつも清めお供えをし、手を合わせる祖父母を見て、住まいのあちこちに霊的な何かが潜んでいるかのような感じさえしたしたものです。
2 方位の意味と環境学

写真:同上:竈と火袋と言われる高い吹き抜け天井の通り庭(写真:筆者)
その後、多くの住まいづくりに係り、土地の気候や方位も肌で体感し、物理的な方位だけではなく運命的な力さえ感じ、高松塚古墳の四方に描かれた彩色壁画の白虎や玄武のように、方位は色や地形にも象徴され、わが生家もそれらに合わせて配置されていたようなのです。
南方位は朱雀(すじゃく)で、田畑があり、その先は広がり。西に白虎(びゃっこ)である道路で、本当に電車も走っていたのです。北には黒の亀の玄武(げんぶ)すなわち山があり、東方には青の青龍(せいりゅう)の大川が流れ、その川の水を引いて大きな水車もありました。今思えば実際にその方位から離れ、その色が消えるすなわち北東と南西にはまるで不気味ななにかが蠢(うごめ)いていたような不思議な感じさえもしたのです。
3 家の宇宙観とさらに永遠を感じる

写真:方位のない回転する家、いざというときは沈む(提案模型:アトリエ4A)
たまたま筆者が祖父母の旧家に育った環境がそうさせるのか?自身には何もない「無」の世界のような家に育ち、まるで「虚」のような時間の体験だったのか?家とはそんな空間なのかも知れません。そんな中で無造作に育ちタガのない幼少期を過ごせたのか。自身の住宅感はいまだにそれが原点で、家相や機能などのルールに縛られることなく、自身が一番安心して「無」になれ、その時だけは「虚」になれるそんな空間を求めているようです。
時々「家相」について思うとき、不思議にその境地になるのです。気が付けばそんな奥深い配慮がなされているのかもしれません。それだけにいったん家から出たときは、外に向かって自由に、さらに新鮮に生きられるのかもしれません。
三和土(たたき)
「叩き」とも書く。粘土質の土に石灰や苦汁(にがり)などを混ぜ叩き固めた今のモルタルセメントのような土間。
次回からは、ちょっと現実に戻って、地震やその対処について考えてみましょう。
関連記事
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

 注文住宅のハウスネットギャラリー
注文住宅のハウスネットギャラリー