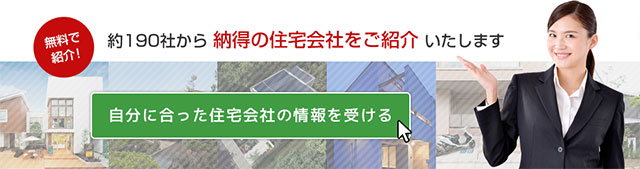住宅関連記事・ノウハウ
![]() 2025年4月1日(火)
2025年4月1日(火)
 住宅ローン『変動型』が半数超える
住宅ローン『変動型』が半数超える
住宅ローン金利は今後ほとんど変わらない?
今後の金利動向と住宅ローン利用者の動向
これからご計画のみなさまにとって、関心が高いことはこれからの金利がどうなるかということだと思います。
住宅金融支援機構が2017年4月~9月に新規で住宅ローンを借りた方を対象に調査した結果によると、『変動型』の利用割合が50.4%『固定期間選択型』が36.9%と、前回調査(2016年4月)と比較して共に増加し『全期間固定型』は12.6%と減少しています。今後1年間の住宅金利見通しについては、全体では『ほとんど変わらない』が増加。全体の57.6%を占めています。逆に『現状よりも上昇する』と回答した方は29.4%と前回調査より8.1%減少しています。このような結果になったことは、容易に想像できます。
- 現在、日銀の政策金利は「ゼロ金利政策」によってこれ以上下げられないレベルまで低下しています。また、2018年3月の新規借入住宅ローンの変動金利(表面金利)の最低金利は0.457%。
- ※じぶん銀行 変動金利 全期間引下げプラン
- 変動金利は短期プライムレートに連動して動きますが、基準となる短期プライムレートは、日銀の統計資料/長・短期プライムレート(主要行)の推移によると、2009年1月13日の1.475%から変動はありません。
- ※短期プライムレート:短期間(1年未満)の企業向け融資で、信用度に何の問題も無い場合の最優遇貸出金利のこと。
新規の住宅ローン本体の契約で得られる銀行の儲けはほとんど無いに等しいと考えても差し支えないので、金融機関はいろいろな手数料で利益を確保するわけです。

変動金利の金利が上昇した場合の備えをしっかり検討
変動金利のリスクと対策
このような状況を踏まえると、変動金利は上がる可能性は出てくるかもしれないなか、2018年はこれ以上金利が下がる期待はできないと考えて良いのではないでしょうか?
ここで、変動金利の金利が上昇した場合の影響ですが、変動金利には5年ルールと125%ルールがあり、当初の10年間は最大125%までしか支払額は上がりません。金利が上がっても、すぐに支払が大きく変わらないということは、金利上昇したことで減らなくなる元本が残り、最終回に差額分を一括又は分割で払います。
では、いつ、変動金利が上昇するのか。変動金利とは金利変動リスクを利用者が負うローンなので、最初の数年は少ない金利で返済できますが、この金利は返済期間中はずっと続きません。金融機関も利益が出ない状態のまま、ずっと低金利での貸し出しをするわけではないので、早ければ数年以内に金利が上昇していくことは間違いありません。では、その備えとは?
変動金利を選ぶ場合は、そのリスクもしっかり考えておくべきでしょう。

新規で住宅ローンを借りる方も、借り換えの方も冷静に判断しましょう
金利タイプ選択の重要性と今後の見通し

次に、10年固定金利やフラット35に代表される『固定期間選択型』『全期間固定型』は、主に新発10年物国債の金利影響をうけます。『固定金利期間選択型』であれば金利固定期間、『全期間固定型』であれば完済まで金利の変動がないことがメリットですが、長期固定金利の指標である長期金利の予想は非常に難しいのです。固定金利については、金利固定期間中は金利変動リスクを債権者が負いますが、固定期間が終了したら、その時の金利水準で固定期間を選ぶか、変動金利を選ぶか、という選択になります。
長期金利動向は、欧米が金融引き締めに向かう中、日銀の金融緩和政策の出口戦略がささやかはじめた現在、いつ日銀が金融緩和政策の出口戦略に踏み出すかがポイントになります。このタイミングは、早ければ2018年後半。
返済の目途や資金に余力があれば、金利が上昇しても返済を継続することや繰上返済をすることができますが、返済に余力がない場合は固定期間終了後に金利が大きく上昇するかもしれない局面で、そのまま生活を切り詰めて支払を継続するか、最悪の場合は住宅ローンの負担に耐えられず、住宅ローンを支払えなくなる可能性も想定しなければなりません。
現在、変動金利で借りていてタイミングを見て固定金利に切り替えようとお考えの方は、そろそろ準備を始める時期です。新規で住宅ローンを借りる方については、今後の金利変動を予測して金利タイプの選択をしっかり検討する必要がありそうです。
関連記事
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

 注文住宅のハウスネットギャラリー
注文住宅のハウスネットギャラリー