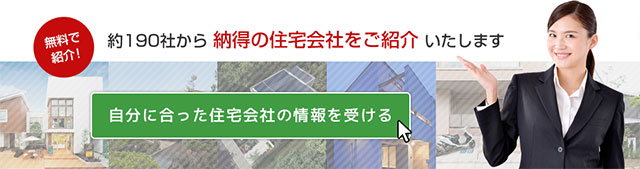住宅関連記事・ノウハウ
![]() 2025年3月31日(月)
2025年3月31日(月)
 居住用不動産に関わる確定申告
居住用不動産に関わる確定申告
目次
居住用不動産に関わる確定申告
確定申告の必要性
居住用不動産を売却したり、購入した場合には、確定申告がつきものです。では、どういった確定申告があるのか、売却した場合・購入した場合に分けて、簡単にまとめてみました。
売却した場合の確定申告
売却時の確定申告の種類
- 利益が出た場合
- 3,000万円特別控除の申告
- 相続等による買換え特例、特定の買換え特例の申告
- 10年超所有の居住用財産の軽減税率による申告
- 損失が出た場合
- 買換えた場合の、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の申告
- ローン残高が、売却収入よりも多い場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の申告
- 住民税について
- 住民税は、所得税を申告すれば申告する必要はありません。
- ※ただし、所得税の申告を元に自動的に計算され、5月頃に納税通知書が来ますので、お忘れなく。
購入した場合の確定申告
購入時の確定申告の種類
- 住宅ローン控除の申告
- 住宅ローン残高の一定率を、税額から控除するための申告。
- 贈与税の申告(購入時、贈与を受けた場合)
- 110万円控除による、一般的な贈与税の申告
- 550万円まで贈与税ゼロ、1,500万円まで税額軽減の申告。(H17年限り)
- 親から子へ、住宅取得資金の贈与3,500万円までの非課税=相続時精算課税の適用届出および申告
- 登録免許税・不動産取得税
- ・登録免許税は、登記の時にかかります。諸費用として、司法書士さんが計算提示してくれます。
- ・不動産取得税は、購入後数ヶ月してから通知が来ます。居住用の場合は、控除がありますので、通知書到着後申請が必要です。
- 居住用不動産を売却した場合には、税務署から自動的に所得税申告書が送られてきますので、原則として申告をする必要があります。期限内に申告をしないと適用されない優遇規定などもありますから、下記『確定申告概要』の期限内に必ず申告を行なうようにしてください。
- ※ただし、10年以上のローンをして、住宅を購入した場合には、住宅ローン控除を受けることができますので、この場合には初年度のみ確定申告をする必要があります。(その後9年間は年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。)
居住用不動産を購入しただけの場合は、必ず確定申告が必要ということはありません。
また、居住用不動産を購入するにあたって、親からの贈与、夫婦間の贈与などがあった場合には、贈与税の申告が必要になってきます。
【居住用不動産に関わる確定申告】確定申告の概要申告時期所得税
確定申告の期間

- 納付申告翌年2月16日~3月15日
- 還付申告翌年1月4日~3月15日
- 郵送の場合は、消印日が提出した日になります。
- 申告時期贈与税
- 翌年2月1日~3月15日
【居住用不動産に関わる確定申告】納付期限
所得税の納付期限
- 翌年3月15日まで
- 休日の場合は、翌日
【居住用不動産に関わる確定申告】振替納税納付期限
振替納税の納付期限
- 翌年4月15日~20日
- 指定口座から自動振替
【居住用不動産に関わる確定申告】延納の納期限
延納の納付期限
- 翌年5月31日
- 1/2未満を延納できる
【8】【居住用不動産に関わる確定申告】提出先
確定申告の提出先と必要書類
現住所の所轄税務署
- 提出するもの
- 確定申告書AまたはB、給与の源泉徴収票、その他所得の種類による下記の各項目で説明します。
- 確定申告をしなければならない人
- 給与収入が2000万円を超えている人
- ※年末調整の対象外のため、確定申告をする必要があります。
- 給与を2ヵ所以上からもらっている人
給与を合算して、所得税を精算する必要があります。 - 給与・退職金以外の所得が、20万円超える場合
- ※原稿料や、配当金、サブの給与収入、その他の収入が、20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
- 不動産の譲渡所得がある場合
- ※不動産の譲渡所得がある人は、この区分に入るため、申告をする必要があります。
- 事業所得、不動産所得がある人で、納付税額がある人
- ※納付税額がない場合は、申告しなくても構いません。ただし、青色申告の場合は申告する必要があります。
確定申告をすると得な人
確定申告で得をするケース
- 住宅ローン控除の適用をはじめて受ける人
- ※最初の年度は、申告をしないと適用を受けることができません。
- 居住用不動産の譲渡損失の損益通算、繰越控除の適用を受ける人
- ※これも申告をしないと適用を受けることができません。
- 居住用不動産の譲渡益から3,000万円の特別控除を受ける人
- ※譲渡益が3,000万円未満だから無税、というわけではありません。申告をしないと特別控除を受けることができず、後から税額が追徴されてしまいます。
- 医療費控除が10万円以上ある人
※医療費から10万円を引いた額が、所得から控除されますので、税金が安くなります。(所得200万円未満の人は、10万円を、所得の5%と読み替えます) - 雑損控除、寄付金控除がある人
- これらの控除は、年末調整では差し引くことができませんので、確定申告します。
- 途中退職して、年末調整されていない方
- ※再就職しなかった場合などは年末調整されていませんので、確定申告をします。ほとんどのケース税金が戻ってきます。
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

 注文住宅のハウスネットギャラリー
注文住宅のハウスネットギャラリー