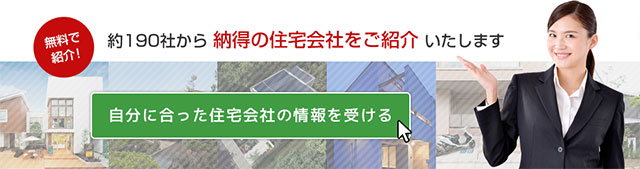住宅関連記事・ノウハウ
![]() 2025年4月1日(火)
2025年4月1日(火)
 自己資金をアップさせる方法!お家づくり現状の資金計画
自己資金をアップさせる方法!お家づくり現状の資金計画
お家づくり!現状の資金計画について

消費税増税が延期になったことで、一度はマイホーム取得をあきらめた方々のマイホームに対する関心が改めて高まっているようです。住宅会社も、不動産会社も消費税8%増税後の反動減によって、どの会社も苦労していますが、各社とも即効性のある値引きの打ち出しや自己資金ゼロを強化。
これからマイホーム取得しようと考えている方、マイホームへの夢を諦めた方々にもしかしたら憧れのマイホームに手が届くかもという期待を抱かせるような傾向が強まっています。具体的にマイホームを取得したいと考えたとき、真っ先に検討しなければならないことは、現状の資金について。マイホームの資金計画には、自己資金と借入金があり、現在の預貯金や取り崩せる有価証券などの自己資金と、住宅ローンなどで借り入れできる金額を合計することで、いくらの住宅を購入できるか試算できます。
自己資金は、自分や配偶者の預貯金のほか、取り崩せる有価証券、祖父母や両親といった身内からの援助や借入も含むことができます。自己資金は、頭金や諸費用の支払いにあてて、足りない部分は住宅ローンでまかないます。住宅ローンは借金ですから、借りたお金が少なければ少ないほど利息が少なくなりますので、返済総額も減ります。そのためには、購入時に払う頭金の額を多くする、すなわち自己資金を増やすことが、最も大きな効果を示すのです。裏を返せば、自己資金が2割に満たない状態で契約すると、将来不測の事態が発生したとき、夢のマイホームが行動を制約する大きな足かせとなるなど、将来の生活で予想だにしなかったことが起きてしまう可能性が高まります。ギリギリまで倹約して頭金を増やすことが目的となってしまい、家族の夢であるマイホームを取得するタイミングを逃してしまう事は、長い目で観た大きな楽しみを失ってしまいます。自己資金は住宅価格の2割~3割程度が目安にするのが良いでしょう。
借入金の上限は、年収に占める年間のローン返済比率を30%程度に納まる程度を目安に、子どもの教育費をはじめ、両親が扶養に入っている家庭かどうか、共稼ぎかといった、各々の家庭における条件をしっかり考えながら検討することが大切です。自分のことを客観的に分析することは非常に難しいので、客観的に判断できるお金の専門家(ファイナンシャルプランナーなど)に相談しながら、丁寧に計画を進めていくほうが間違いありません。
お家づくり資金計画の基本
- ・自己資金と借入金を合計して住宅購入予算を試算する
- ・自己資金は預貯金、有価証券、親族からの援助・借入を含む
- ・自己資金は頭金や諸費用に充当し、不足分は住宅ローンを利用
自己資金の重要性
- ・頭金が多いほど利息が減り、返済総額も減少
- ・自己資金が少ないと将来の生活が制約される可能性
- ・自己資金は住宅価格の2~3割程度を目安にする
借入金の検討
- ・年間のローン返済比率を年収の30%程度に抑える
- ・子どもの教育費、扶養家族、共働きなどを考慮
- ・客観的な判断のためにファイナンシャルプランナーに相談
資金を節約!自己資金をアップさせる方法

帝国データバンクが発表しました2014年11月の景気動向指数ですが、前月比で0.6ポイント悪化の43.5ポイントまで下落しています。この低落傾向は今後より深刻になっていきます。このような時期を踏まえて、家を建てる・大規模なリフォームをすることは、駆け込み時期に慌てて工事を行うより、ずっと高品質な住まいを適切な価格で建てられる良い機会でもあるのです。
公的な優遇制度を活用できることや、そもそも家を建てようと考える方が少ないため、丁寧な工事品質を期待できることなど、有利な条件が揃います。マイホーム資金を節約する自己資金をアップさせる方法についていくつかご案内しましょう。
日々の節約自己資金は毎月コツコツと貯めていくのが確実。マイホーム資金専用口座をつくり、日々の生活費を節約して貯めることが理想。かんたんな家計簿をつくって電気・水道・ガスの使い方を意識し、余計な買い物を減らすだけでも貯まっていきます。でも、節約することだけを目的とせず、無理をせずできる範囲の節約を心掛けましょう。
給与天引き制度がある会社にお勤めであれば、給料やボーナスから自動的に天引される財形制度の活用も検討しましょう。財形積立残高の10倍(上限4000万円)まで融資が受けられたり、元利合計550万円までの利子等は非課税扱いになるなどのメリットがあります。(貯蓄目的以外で払い出す場合には課税)
共有名義(夫婦や親子)夫婦や親子で資金を出し合えば自己資金は増えますが、登記するとき出した金額に応じた割合で共有名義にしないと贈与とみなされて贈与税の対象になります。
資金援助(両親や祖父母)肉親からのお金のやりとりでも年間110万円を越えると贈与となり、贈与税の対象となります。ただ、住宅取得にかかる贈与については贈与税の特例があるほか、相続時精算課税制度の利用で非課税枠が増えます。
借金(両親や祖父母)両親や祖父母から住宅資金を借りるとき、ある程度の金利を設定して借用書をつくり毎月返済する実績が必要です。金利がゼロだったり返済実績がないと、贈与とみなされてしまいます。
自治体の助成制度都道府県や市区町村によっては、マイホームのための助成や優遇をしています。特定の地区内で耐火性の高い住宅を建てると、自治体が利子を補給してくれる制度や、地元産の木材を決められた量使うことで、住宅ローン金利を優遇するなどの制度があります。住宅ローン返済の負担を減らすため方法として、しっかり検討する価値があります。
上記の方法をいくつか組み合わせることで、自己資金の確保に目処がついたら、いよいよ夢のマイホームづくりの計画づくりを進めることができるのです。年末年始は、家族や肉親との資金計画相談と夢のマイホームづくり計画をすすめる格好の時期。12月中に備えておくと、年末年始の段取りをスムーズに進めることができますよ!
自己資金を増やす方法
- ・日々の節約でコツコツ貯める、マイホーム専用口座を作る
- ・財形制度を活用する、積立残高に応じた融資や非課税措置がある
- ・夫婦や親子で共有名義にする、贈与とみなされないよう注意
- ・親や祖父母からの贈与は特例や相続時精算課税制度を利用
- ・親や祖父母からの借入は借用書作成と返済実績が必要
- ・自治体の助成制度を活用する、利子補給や金利優遇などがある
自己資金確保後のステップ
- ・自己資金の目処がついたらマイホーム計画を具体的に進める
- ・年末年始は資金計画相談と計画を進める良い機会
住宅ローン最初にやる事!情報収集のすすめ

総選挙の結果次第で、長期金利が低いまま続くのか、一転して金利上昇局面に変わっていくのか。現時点では低金利は続くという予想が大勢を占めておりますが、長期金利の変化とは今後も正確に予測することができません。金利は最も重要な経済変数の1つです。長期金利が乱高下すると金融機関に巨額の評価損が出たり、国債の利払いが増加したり、設備投資が減少したりと、住宅ローン以外にも大きな影響が出ることから、長期金利推移に連動する住宅ローンの選択と見直しは慌てて行うことではありませんので今後の経済を見ながら焦らず選択していきましょう。住宅ローンの借入は多額で支払いは長期間です。少しの金利の差がそのまま大きな違いになります。
住宅ローン情報収集の重要性
- ・長期金利は予測が難しく、住宅ローン金利も変動する可能性がある
- ・住宅ローンは長期間の支払いとなるため、金利の差が大きな影響を与える
- ・経済状況を見ながら慎重に選択することが大切
住宅ローン金利種類

- ・ローン期間中の金利が変わらない固定金利
- ・金利が変わる変動金利
- ・当初数年間は固定金利
- ・固定か変動か選ぶことができる固定金利選択型
それぞれにメリット・デメリットがあることから、それぞれの特性を理解してご自身にあったローンを適切に選択することが大事です。
住宅と同じように、住宅ローンも必ず数社で検討することが大切です。お勤め先、不動産会社、銀行窓口やネットで探すと、さまざまな金融機関で、いろいろな住宅ローンキャンペーン金利が用意されています。各金融機関の住宅ローンキャンペーン優遇金利を検討する場合には、当初数年間の優遇幅が大きい優遇金利タイプなのか、全期間にわたり同一優遇になる優遇金利タイプかの確認し、いずれの優遇金利タイプでも、あらかじめ総支払額を計算してみるようにしましょう。ほとんどのローンは融資実行時(資金受け取り時)の金利で確定しますが、変動金利を選択された場合、申し込んだときとは金利が変わります。ローンの借入金利が確定する時期にも注目しましょう。住宅ローンを決めたら、改めて住宅ローン総支払額の計算をしてみましょう。
現在の予測では、数ヶ月単位では長期金利は上昇しない、との見方が大勢ですが、2~3年にわたる家づくり計画検討の局面において、いつ長期金利や住宅ローン金利が上昇しはじめても不思議ではありません。家づくり計画初期段階から住宅ローンに関する情報は集めておき、家づくり計画最終段階で適切な住宅ローンを正しく選択できる知識を学んでおきましょう。
住宅ローンの金利タイプ
- ・固定金利:ローン期間中の金利が変わらない
- ・変動金利:金利が変動する
- ・固定金利期間選択型:当初数年間は固定金利、その後変動金利
- ・固定金利か変動金利かを選択できるタイプ
住宅ローン選びのポイント
- ・複数の金融機関で比較検討する
- ・キャンペーン金利のタイプを比較する(当初優遇型か全期間優遇型か)
- ・総支払額を計算する
- ・変動金利の場合は、金利確定時期を確認する
今後の金利動向
- ・短期的な金利上昇の可能性は低い
- ・長期的な視点では金利上昇の可能性もある
- ・計画初期から住宅ローン情報を収集し、適切なローンを選択できるように準備する
住宅ローンの注意点!メンテンナンスが必要!?

住宅ローンはメンテンナンスが必要総選挙は予想通りの結果になりましたが、12月15日に発表された日銀短観を観ると、大企業・中小企業とも先行きを悲観している姿があります。住宅ローンの支払いを続けて、先行き不安=収入減少とプレッシャーを感じる大半の方々が経済の先行きを悲観している現在。建て替えた・リフォームの検討をしながら、住宅ローンのメンテナンスを考えてもよいかもしれません。
住宅ローンの借り換えとは借り手から観ると、あるローンから別なローンに載せ替えるイメージと考える方が多いようですが、別な視点から見ると、高い金利で借りていた住宅ローンの残債を低い金利のローンで返済するとも言い換えることができます。借り入れ時に有利な住宅ローンを借りていたとしても毎月の手取りが減る可能性が考えられるとき、ローンの支払い条件を見直す検討をしたほうが良いでしょう。長い支払い期間中に大きな金利の変化もありますし、有利な条件のローンが出てくる可能性があります。
住宅ローン借り換えの注意点住宅ローンの借り換えは、新たに住宅ローンを組むことと同じです。ローン保証料のほか、登記費用や税金、手数料を合計した諸費用で50万円~80万円かかる例もあるので、借り換え検討にあたっては、金利だけではなく諸費用も試算しましょう。現在の借入金利が2%台の方、優遇金利の適用を受けている場合、完済までの期間が短い、一括返済の目処が立っている場合、借り換えることで損をする可能性が高くなります。
上記の要件に当てはまる場合、無理に借り換えをせず、そのまま繰り上げ返済を検討したほうが良いかもしれません。
住宅ローンもメンテナンスが必要
経済状況の変化に応じて、住宅ローンの見直しも検討すべき
住宅ローンの借り換えとは
- ・高い金利のローンを低い金利のローンで返済する
- ・手取りが減る可能性がある場合は支払い条件を見直す
- ・有利な条件のローンが出てくる可能性もある
借り換えの注意点
- ・借り換えには諸費用(保証料、登記費用、税金、手数料)がかかる
- ・現在の金利が低い場合や、完済が近い場合は借り換えが不利になる場合も
- ・無理に借り換えせず、繰り上げ返済を検討するのも良い
税金について!家づくりのどの段階で必要?

マイホームを取得する際、購入代金以外にもさまざまな支出があります。そのなかでも、大きな支出を占めるのが税金です。税金には、契約時に納める税、引き渡し後に納める税、毎年納める税があります。どの段階でどんな税金がかかるのか、あらかじめ把握しておきましょう。住宅ローン減税を受けるには所得税の確定申告を行う必要があり、それぞれの税には軽減措置や控除制度など用意されています。すべての税金の軽減措置・控除制度に手続きが必要になるわけではありませんが、税の優遇制度をうけるためには、自分で申請しなければならないものもあります。来年度の軽減措置や優遇措置については平成26年度の税制改正大綱が発表されてから、随時ご案内させていただきます。みなさまが利用できる優遇措置について、事前に確認しておきましょう!
家づくりと税金
- ・税金は家づくりにおける大きな支出の一つ
- ・契約時、引き渡し後、毎年納める税金がある
- ・住宅ローン減税は確定申告が必要
- ・税の優遇制度は自分で申請が必要なものもある
- ・事前に優遇措置を確認する
建築請負契約締結時にかかる税金について
| 建築請負契約締結時にかかる税 | 内容 |
|---|---|
| 印紙税 | 売買契約書や工事請負契約書、住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約)にかかります。 |
| 消費税 | 法人から購入する場合は建物代金に、仲介業者が入る場合は仲介手数料にかかります。土地は非課税。 |
| 贈与税 | 親や祖父母から住宅資金を援助してもらった場合、課税されます。夫婦間贈与には特例があります。また、一定年齢以上の父母から援助や贈与があったときには、相続時精算課税制度を利用できます。 |
建築請負契約時の税金
- ・印紙税:契約書に課税
- ・消費税:建物代金や仲介手数料に課税、土地は非課税
- ・贈与税:親族からの資金援助に課税、特例や相続時精算課税制度の利用を検討
完成・引き渡し・表示登記の税金について
| 完成・引き渡し・表示登記税 | 内容 |
|---|---|
| 登録免許税 | 引き渡し時は所有権の保存登記(または移転登記)、ローン契約時は抵当権設定登記にかかります。財形住宅融資は非課税。 |
完成・引き渡し・表示登記の税金
登録免許税:所有権保存登記、抵当権設定登記に課税、財形住宅融資は非課税
住宅ローン契約の税金について
| □ | 住宅ローン契約時の税 |
|---|---|
| □ | 印紙税 |
| □ | 登録免許税 |
住宅ローン契約時の税金
- ・印紙税:契約書に課税
- ・登録免許税:抵当権設定登記に課税
入居後の税金について
| 入居後の税 | 内容 |
|---|---|
| 不動産取得税 | 不動産を取得したことに課税されます。売買だけではなく、交換、贈与も課税対象になります。 |
入居後の税金
不動産取得税:不動産を取得したときに課税(売買、交換、贈与も含む)
毎年1月1日付けの税金について
| 毎年1月1日付けの税金 | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税 | 都市計画税:どちらも、毎年1月1日現在に所有している不動産に課税されます。 |
毎年1月1日付けの税金
- ・固定資産税、都市計画税:毎年1月1日現在の不動産所有者に課税
- ・住宅を購入する前に一度税金に知っておくのもいいでしょう。
関連記事
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

 注文住宅のハウスネットギャラリー
注文住宅のハウスネットギャラリー