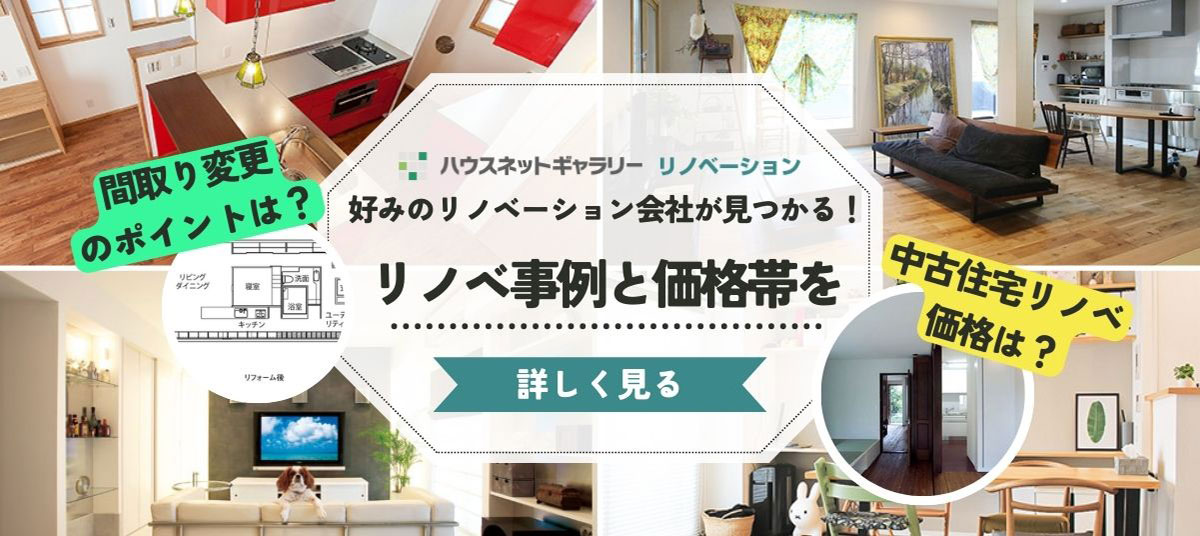住宅関連記事・ノウハウ
![]() 2025年4月1日(火)
2025年4月1日(火)
 長生きハウス!住まいを楽しく歴史と文化を
長生きハウス!住まいを楽しく歴史と文化を
厳寒の寒さが緩むころ、なぜかこの3月は重大な事故や事件、さらには災害も多いのです。3月8日は営団地下鉄日比谷線脱線衝突。25年前。10日は関東無差別大空襲、そして11日は2万余の犠牲者と行方不明者の大災害の東日本大震災、14年たつ今も、いまだに3万人近い人々が避難生活を送り原発の廃炉もままならず、さらには30年前の20日はあの地下鉄サリン事件等々。
風雅な雛祭りや卒業式とは裏腹に、追悼の式典とともに教訓の集いが開催されるのです。住まいも暖かな春とともに防災の緊張感を持つべき時かも知れませんね。
“立体長屋”の持ち家?
戦後80年となる今日復興とともに、がむしゃらに働き高度経済成長をなし遂げ、都市に人口が集中し、家はなんとか住めればよいとなって、郊外に長屋団地をあちこちに建て、遂には欧米から“ウサギ小屋に住むビジネスマン”などと揶揄されるに至ったのです。
そこでやっと住まいへの関心が起こり、国を挙げて住宅金融公庫さらに年金住宅、宅地開発と持ち家政策を推進したのです。おかげで、都市はさらに過密となり地価は高騰、いよいよ“立体長屋の持ち家”すなわちマンション時代となるのです。
区分所有なる半端な権利の高層の持ち家ブームの到来となり、今日のタワマンブームとなるのです。
狭い・高い・遠い!の三すくみの中での発想?

狭楽しく住む記事:朝日新聞
筆者もご多分に漏れず中古の小さなマンションを購入し、その劣悪さに驚き大幅改装をして住んだのです。まさしくリフォームの走りでした。
その時痛切に感じたことが、“家族一人一人の生活、家族らしさ、そしてわが家の誇りをいかに持つか?”でした。
限られた狭い2LDKの中で、狭苦しいとただ嘆くのではなく原因となる“苦”をとれば狭くても楽に、いやもっと楽しくなるのではないかと考え、狭“楽”しく住む家づくりを提唱したのです。
この顛末を一冊の本に綴り、出版をしたのです。題して『狭楽しく住む法』(新声社)でした。
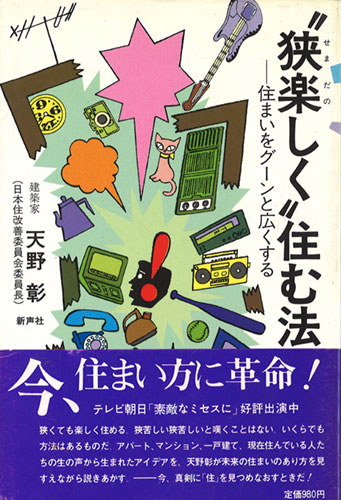
拙著「狭楽しく住む法」(新声社)(写真:天野彰)
日本住改善委員会から住まい文化キャンペーンへ
これを機に。当時の新進気鋭の建築家たちと集い、「住改善委員会」なるものを立ち上げ、わが国が持つ古来の家と、新たな時代のわが国らしい家をつくろう。さらには都市での居住そのものを見直し、新たな住まい文化の創造を目指すものでした。

日本住改善委員会パンフレット表紙
当時の過密都市での雑然とした住まいから家族が消え、伝統文化、住まいへの情緒、さらにはわが住まい文化の歴史と象徴と誇りとは?と。やがて通産省、厚生省そして建設省が住まいを取り上げ、各種委員会を開催、結果、住まい文化キャンペーンを全国展開にするに至ったのです。
建築家をはじめとする住宅界では「増改築フェア」から始まり、やがて、「リフォーム&リニュアル」展と住まいの改善・再生運動を展開することになるのです。
しかし最近になって、今の住まいに何かが足りないのです。戦後80年、時代は変わったのです。世界の均衡は新たな時代となり、SNSでますます個人主義となり、孤立主義から利己主義とさえなり。わが住まいはその狭間でいかに自己防衛と自助自立をするかです。
そこで現在の家を一度見直してはいかがでしょう?次回は『わが家を「減築」し、コンパクトに守りやすく!』です。お楽しみに!
関連記事
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

 注文住宅のハウスネットギャラリー
注文住宅のハウスネットギャラリー