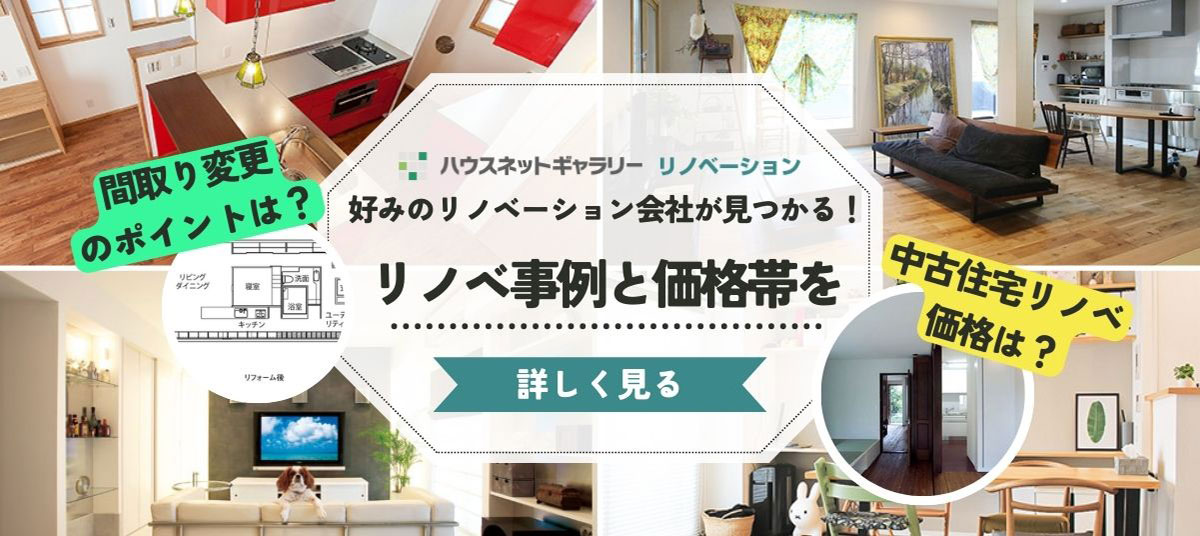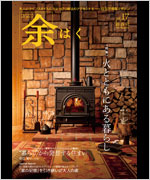住宅関連記事・ノウハウ
![]() 2025年4月1日(火)
2025年4月1日(火)
 どうしてそんなに植物が必要?~グリーンと暮らす
どうしてそんなに植物が必要?~グリーンと暮らす
自然の生命力に癒されて~グリーンと暮らす

生活空間にグリーンを置く。それだけで住まいの雰囲気は一変します。グリーンには、お気に入りのインテリアや雑貨、趣味のアイテムなど空間を彩るさまざまなものをしっくりと融和させる不思議な力があるのです。今回は、そんなインテリア性の高いグリーンの魅力と、暮らしの中に上手に取り入れるためのポイントをご紹介します。
グリーンのもつ自然の生命力に癒されて

衣類や紙、調味料など、思えば私たちのまわりには植物から生まれたものがたくさんあります。植物は加工されて実用品になるだけでなく、葉の形や色の美しさを眺めるという観葉植物としての歴史も長く、江戸時代には軒先にシノブをつるして緑を楽しむといった使われ方もしていたよう。現在、室内に選ばれるグリーンは、亜熱帯や熱帯など湿度や温度が高い地域に自生していたものが多いため、光が弱く乾燥している日本の室内で生長させるにはちょっとした配慮が必要です。例えば、風通しや日当たり、湿度など。部屋の中でその生育環境を少しでも再現してあげることが大事なのです。そうすることで、芽吹いたり、葉を増やしたり、生物としての営みが見てとれます。空間を彩るという点では家具や雑貨と同じですが、この〝生きているゆえの変化〞がグリーンならではの魅力。
グリーンのヒーリング効果
その自然の生命力が、私たちの心身に安らぎを与えてくれるのです。グリーンのヒーリング効果は科学的にも解明されつつあります。例えば、植物が身近にあると精神の安定を示す脳波のアルファ波が増える、血圧や心拍数が減少するなど。これらの働きはグリーンから発生するマイナスイオンによるものかもしれませんし、美しい葉色を見て心が和むせいかもしれません。いずれにせよ、自然のリズムの中で生きるグリーンの力を借りることで、多忙な毎日の中でつい忘れそうになる生物としての本来のリズムを取り戻すことができるのです。
時は春

いのちあるものが生長するこの季節は〝グリーンことはじめ〞にふさわしい時期。数ある中から自分好みのグリーンをパートナーに選び、一緒に暮らしてみませんか。つづいてはインテリアグリーンを楽しむヒントをご紹介します。

グリーンライフを楽しむ5つのヒント

グリーンが身近にある暮らしの心地よさを一人でも多くの方に知ってもらうために、グリーンと上手につきあうための方法をご紹介します。
置きたい場所を決めてから、ショップスタッフに相談する

基本的には、現物を見て気に入ったグリーンを購入するのがいちばんですが、購入前に置きたい場所をある程度決めておき、窓からの距離や日があたる時間帯などをショップのスタッフに伝えて、どんな植物がよいかを相談してみましょう。そのとき、グリーンを置こうと思っている場所の写真を持っていくのもおすすめ。写真を見れば当たりや風通しの状況もある程度はわかるので、育て方のアドバイスももらいやすくなります。
移動しやすい小さめのグリーンを選ぶ

多いのは、大鉢をひとつ選んでリビングに置くというスタイルだと思いますが、意外におすすめなのが、小さめのグリーンを集める方法。どちらも魅力的ですが、フレキシブルに対応しやすいのは、やはり後者といえるでしょう。
小ぶりなグリーンは水切れを起こしやすいので水やりのタイミングには要注意ですが、植物のコンディションに合わせて場所を移動しやすいのがよいところ。グリーンにとって落葉や葉色の変化は、その場所が適していないというサイン。適した場所は季節によっても違うので、急激な温度変化さえ避ければ、よりよいと思われる場所に移動させることは長くグリーンを楽しむうえで重要なのです。また、小ぶりなタイプを集める方法なら、その中のどれかがたとえ枯れてしまったとしても、ダメになったグリーンだけを取り除けばよいので、初心者にとっては手軽です。
水はたっぷりと与え、受け皿に残さない

グリーンを枯らせる原因のひとつが、水の過不足。水やりは、土の表面が乾いたら底穴から流れ出るくらいたっぷり与え、底にたまった水は捨てるのが基本です。大鉢の場合は水を捨てることが難しいので、水が受け皿にたまらない程度に、土の乾き具合をみながら水やりをしましょう。乾き具合は、植物の水を吸う量、季節、日当たり、風通しなどの環境、土の状態、鉢の大きさなどによって変わるため、あまり機械的に決めず、土を触って乾いているかどうかを確かめてから行うことが大切です。

グリーンの名前は正確に控えておく

グリーンの名前をきちんと控えておくことも大切です。なぜなら、購入後、ショップスタッフなどに育て方を相談する際、正式な名前がわからないと正 しいアドバイスがもらえないため。逆に、名前さえわかっていればインターネットで検索したり、本で調べたり、必要な情報にすぐアクセスできます。同じ理由で、原産地を知っておくのもおすすめ。大切なグリーンのプロフィールを理解するのが、上手に育てる秘訣なのです。
優等生的に育てるよりグリーンとの生活を楽しむ

教科書的な育て方にとらわれると、グリーンとの暮らしが楽しくなくなってしまうので、パーフェクトな状態を目指しすぎないことも大切です。例えば、「売られていたときの白いプラスチック鉢は植物にとってよくない」などと言われることがありますが、実はそうでもありません。確かに、素焼きや陶器の鉢は通気性がよいのが利点ですが、大きなサイズになるほど重量があり、動かすのが大変です。
そのため、植物の状態に合わせての場所移動がしづらく、水やりの際も鉢ごと外に出しにくくなるなど、ケアが二の次になりやすいというデメリットも。その点、プラスチック鉢は軽くて、壊れにくく、安価なのが利点です。その質感が気になる場合は、陶器などの鉢カバーに入れれば目隠しできます。あまり統一感に縛られず、グリーンライフを楽しむことを優先させましょう。

「グリーンを育てるのは苦手」という方におすすめなのが、多肉植物
肉厚で、まるいフォルムが特徴的な多肉植物は、肉厚の茎や葉の中に水を貯めておくことができるため、あまり頻繁に水を与える必要がなく、グリーン初心者や多忙で留守にしがちな人でも比較的扱いやすいのです。サボテンなども含め、多肉植物と呼ばれるものは種類が多く、その性質や育て方もさまざまですが、ショップで手頃に入手できる種類は基本的に丈夫で栽培しやすいものがほとんど。また、ゴムノキの種類など、昔からなじみのあるグリーンは丈夫で育てやすいのが特徴です。
どうしてそんなに植物が必要?

- 「それは植物が生活を楽しむためのインテリアだからさ」
- 他の欧米諸国から「ヨーロッパの庭」と称されるオランダ。その異名のとおり、花とグリーンはこの国の人々の暮らしにしっかりと根づいています。オランダ在住のライター、稲葉霞織さんから届いたメッセージをご紹介。
オランダの街を歩くと、気づくことがあります。それは、花の専門店はもちろん、ガソリンスタンドや駅のキオスクなど、至るところで季節の花が購入できるということ。オランダ人は花を自宅用に買い求めるだけでなく、ギフトとしても選びます。特に理由などなくても、自宅に親戚や友人を毎日のように招待し、コーヒー片手に談笑するのが代表的なオランダ文化の一つで、その場に欠かせないのが花。招待してくれた相手の家を訪れるとき、手土産として花束を持参するのは、オランダ人にとってのマナーなのです。
「どうして、そこまで生活に植物が必要なの?」もし、オランダ人にこう聞けば、きっとこんな返事が返ってくるでしょう。
「ソファやランプと同じように、生活を楽しむためになくてはならないインテリア、それが植物だからさ」。花は、オランダ人にとって大切な、暮らしのアイコンだと言えるのです。夏に向けてのこれからの時期、注目を集めるのは切り花だけではありません。毎年6月の最終週末の金曜日と土曜日(年や都市で変更もあり)には、各地で個人宅の庭が開放され、自由に見学できる「オープン・ガーデン」が開催されます。オープン・ガーデンはイギリスなど、ヨーロッパ各国でありますが、オランダのガーデンはどこか、モンドリアンやエッシャーの芸術性に共通するような、幾何学的なデザインが多く見られるのが特徴です。
- ・庭のどの部分に花を植えるか?
- ・どの部分をレンガや石で覆うか?
- ・どこに池をつくるか?
花との関わりがごく身近なオランダでは、花や樹木の美しさを生かすのも殺すのも庭次第だと考える人が多いため、庭の設計・デザインには凝る傾向が強く、使用する石やレンガなども気に入ったものが見つからなければ、わざわざオーダーして入手する人も少なくありません。
こうしたオランダのエクステリアの考え方の中に、日本人が共感するポイントがあるとしたら、どこでしょう?私は「ストーリー性」だと思います。実際、日本の石庭のようなストーリー性のある庭をオランダ人はとても好み、日本庭園をエクステリアのお手本にする人もたくさんいるのです。また、オランダは九州と同じくらいの面積しかない小国で、各家の坪数もさほど大きくないため、インテリアとしてグリーンや花をあしらう際、天井からつるしたり、壁に小さな鉢を取り付けたりと、工夫を凝らします。そのあたりも、日本と共通する部分といえるかもしれません。年間を通して曇天で暗い日が多いオランダでは、人々は家にこもりがち。そんなとき、身近に花やグリーンがあると、それを眺めているだけで気分が晴れ、精神的に安らぎ、幸せな気分で満たされます。
だからこそ、毎週のように新しい花を買い、身近にグリーンを置き、生活を楽しもうとするのです。
- 情報提供:住宅情報マガジン『余はくvol.21春夏号』
- P13(2014.4.20発行)
- 文/稲葉霞織氏(イナバカオル)
関連記事
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

 注文住宅のハウスネットギャラリー
注文住宅のハウスネットギャラリー