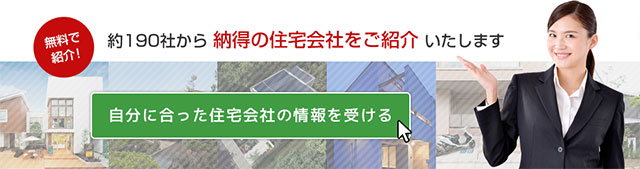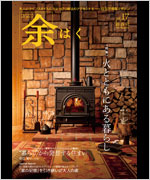住宅関連記事・ノウハウ
![]() 2025年4月1日(火)
2025年4月1日(火)
 ドイツに学ぶインテリアキッチン
ドイツに学ぶインテリアキッチン
ドイツに学ぶインテリアキッチン

キッチンに対する考え方の違い
ドイツでは「キッチン=家具」、日本では「キッチン=水廻り」と考え方はまるで違います。
ドイツと日本のキッチンは成り立ちが違います。ドイツはシステムキッチンの発祥国です。システムキッチンは19世紀待つにシンクと水栓、ガスオーブン、調理場などを短い動線でつなぎ、家具に組み込んだものがはじまりです。そうした経緯があるため、ドイツ人にとっては、今でも「キッチン=家具」なのです。ですので賃貸住宅に暮らす場合でもキッチンは入居者が用意します。もちろん引っ越すときにはキッチンも一緒に持っていきます。
ドイツにおけるキッチンの位置づけ
また、「キッチン=家具」であることから、インテリアを構成する要素としてキッチンを捉えており、家具同様にライフステージ別にキッチンのセグメントがあります。若い世代向けのキッチンがあり、年齢を重ねて家を建てるときに「憧れのブランドキッチン」を検討するといった流れです。日本で「いつかはル・コルビジュエがデザインとしたソファがほしい」と考える人がいるように、「いつかはポーゲンポールのキッチンがほしい」と考えるのは、ドイツでは一般的なことです。このようにドイツではキッチンがインテリアの構成要素として考えられているので、キッチンと家具全体の雰囲気を調和させることを考えます。アンティーク家具に囲まれた家に暮らしていれば、それに合わせてキッチンにもそれに似合った濃い色の木材を選んだり、真鍮のハンドルを選んだりといった具合です。
間取りへの影響
こうした考え方は、間取りにも影響を与えます。日本でもキッチンとダイニング・リビングの距離が近づいてきていますが、ドイツではインテリアへの関わり方がより密接で積極的です。「リビング・ダイニングのなかに調理できるスペースがある」と言ったほうがよいくらいのプランが当たり前に提案されています。日本では「インテリアとしてのキッチン」の提案に対してやや消極的なのは、もともとキッチン(台所、厨房)が水を使う場所として、外部や土間などの半外部に設けられていたためです。しかも北側が大半。こうした歴史的な経緯もあり、日本では「キッチン=水廻り」として捉えられています。
食生活が変わればキッチンも変わる

ドイツと日本の食文化の違い
ドイツにおいて、居住スペースとキッチンが一体になった提案が可能なのは、ドイツ人の家庭料理の種類が少ないという理由もあります。コールドミートに茹でたジャガイモ、そして肉を焼いてディナープレートに乗せておしまい・・・というように至ってシンプルなのです。当然、調理器具や食器も日本の家庭より少ないので、インテリアとしての完成度を追求しやすいのです。
一方、日本の家庭をみると、料理の種類は多く、それに合わせて調理器具もたくさんあります。こうした事情もあり、日本では収納に対して関心が集中する傾向にあります。
ドイツのキッチンに見られる特徴
このほか食文化に起因するドイツと日本の違いでいうと、ドイツにはダブルシンクが多いという点が挙げられます。片方に石鹸水を貯めて、片一方で野菜を洗うといった使い方になりますが、日本では指示されません。食器洗い機のサイズは大きいものが主流です。そして、タイマーなどの機能よりもメンテナンス性や耐久性が重視されます。設計思想がまるで異なるのです。
ドイツのキッチンは「バラ買い」

こうした「キッチン=家具」と「キッチン=水廻り」という文化の違いは、キッチンの買い方には影響します。ドイツのキッチンは「バラ買い」(パーツの組み合わせ買い)です。キッチンメーカーは箱(本体)を提供するだけでなくシンクや水栓金物などは専門のメーカーから施主が購入して取り付けます。
日本のキッチンメーカー
一方、日本では、キッチンメーカーがすべてをまとめています。選びやすく機能は充実していますが、生活に合ったものが選べはかったり、機能過剰だったりするケースが生じます。また、日本のキッチンメーカーは、母体がステンレスや水栓、衛生陶器のメーカーに比べるとインテリアの提案力がやや弱いといえます。扉材もお手入れ性が重視された、ただ色をそろえればいいと言った感じ、感情や素材感に乏しいのです。
これからは「マルチクッキング」時代

ドイツでは、石材や木材もよく使われます。インテリアとの調和を含めて、魅力ある素材です。実際、私の自宅(本間美紀さん)のキッチンはチークの天板を使っています。お手入れさえきちんとやれば実用上問題はありません。お手入れといっても、濡れたらすぐに拭くとか、たまにオリーブオイルを塗る程度です。もちろん、日本のキッチンの優れた点もあります。シンクや水栓などのパーツです。最近の製品でとてもいいと思ったのが、TOTOの「クラッソ」です。これは3度の傾斜がついて水が流れやすい形状のシンクと、水を広範囲にいき渡らせる水栓を開発しています。
日本のキッチン製品の進化
水がゴミと一緒に排水溝に滑り流れるので、きれいなシンクを維持できる。出た水が広がり少量の水で幅広く洗える「水ほうき水洗」を備える。あとは熱源です。IHクッキングヒーター(以下、IH)は節電できるように進化しています。コイルが分割されていて、必要なコイルのみ加熱するのです。小さな鍋などを使うときに熱の無駄がありません。ガスコンロもゴトクの形状や、トップの素材を工夫し清掃性はIHと同等ですし、こちらも世界的にみて製品レベルは高いと思います。
コンロの選び方
このようにコンロに関しては、電気がいいともガスがいいともいえなくなっています。フライヤーやバーベキューグリルなど、目的に合わせて電気・ガスの調理器具を組み合わせる考え方です。
「フレームキッチン」の提案

ヨーロッパキッチンの傾向
最後にヨーロッパキッチンの傾向について紹介します。たとえば2012年1月にドイツ・ケルンに出展した各社の最新作をみていますと、バウハウス的なモダニズムへ回帰する動きがあります。具体的にいうと、基本フレームをベースに必要な部材のみを組み合わせるという考え方です。この考えて方は、これからのキッチンに応用できます。たとえば、エレクターなどでフレームを組み、天板とシンクを乗せるだけのシンプルなキッチンも、すでに日本で登場しています。カウンター下には収納でも食洗機でも好きなものを置けば立派なキッチンになります。
冒頭でドイツでは「キッチン=家具」という話をしましたが、それは、「家具に天板とシンクが載ったらキッチンになる」というシンプルな考え方がベースにあるということでもあります。こうした自由さをドイツのキッチンからは学ぶべきでしょう。
キッチン選びのポイント
新居のキッチンを考える際には、いきなりカタログから入るのではなく、まず自分がなにを必要としていて、なにを好ましいと思っているのかをしっかり考える。そのうえで、部材や設備を追求することができると、新居での生活はより自分らしく、楽しいものになっていくはずです。
バウハウス調の機能美を追求したデザイン。目的や好みで調理機器や収納などを組み入れるという考え方。
- 取材協力/キッチンジャーナリスト本間美紀
- 取材・文/大菅力
- 撮影/今井義朗
- 協力/設計施工・有吉住宅
住宅情報マガジン『余はくvol.15春夏号』P8~P10(2012.4.20発行)
関連記事
- ~生活を彩る~インテリアキッチン・プランニング術のすすめ
- LDKは炉辺?!それが住まいの原点?~住まいの本当のお話し
- お庭で何する?活用方法のご提案
- やっぱり、おうちごはん!
- ~北欧スタイルの魅力~人にやさしい北欧アイテム
- どうしてそんなに植物が必要?~グリーンと暮らす
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

 注文住宅のハウスネットギャラリー
注文住宅のハウスネットギャラリー