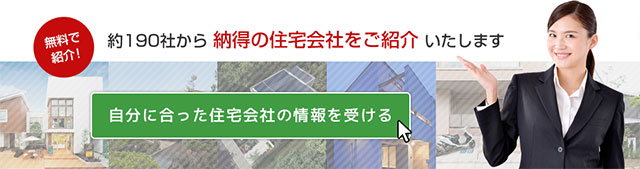住宅関連記事・ノウハウ
![]() 2025年3月25日(火)
2025年3月25日(火)
 2025年4月1日施行の改正建築基準法!木造2階建て以上の新築やリフォームでも建築期間とコストのアップに注目
2025年4月1日施行の改正建築基準法!木造2階建て以上の新築やリフォームでも建築期間とコストのアップに注目
新築価格の高騰をうけ、中古住宅や建売住宅の購入を検討されている方もいらっしゃることでしょう。また住宅は購入しただけで終わりではなく、住み続ければリフォームする時がきます。
今回は、2025年4月1日施行の改正建築基準法・建築物省エネ法に基づき、これから住宅をリフォームする場合に注意しなければならない、「工期延長」について解説します。

新築住宅の価格は大幅に上昇
みなさまご存じの通り、新築住宅(戸建・マンション)の価格が上昇しています。さらに、土地取得費の上昇も止まりません。
2024年1月31日に公表された国土交通省の「住宅着工統計」によると、2023年の新設住宅着工戸数は、前年比4.6%減の81万9,623戸と3年ぶりの減少。
持ち家(注文住宅)は、前年比11.4%減の22万4,352戸と大きく落ち込み、1959年の20万4,280戸以来、64年ぶりの低水準。
これは、住宅建築費や土地取得費の上昇、中古マンション価格の上昇、中古戸建住宅の伸び悩みなどから、戸建志向が低下していることが要因として考えられています。
また、資材価格には落ち着きがみられるようになったものの、高齢化や働き方改革をうけた残業時間抑制に伴い人件費が継続的に上昇していること、ならびに建築業界は他の業界と比較して価格転嫁が進んでいることから、住宅建築費は上昇しています。
さらに、株高・為替安をうけた土地取得費の上昇も止まりません。
断熱性・耐震性に優れた高性能住宅にしないと、行政が建築(新築・リフォーム)を許可してくれない!?

2025年4月施行の【改正建築基準法】【建築物省エネ法】により、建築確認申請における省エネ・構造関連の図面と書類の提出が義務付けられます。
つまり、2025年4月1日以降の着工は改正建築基準法 ・ 建築物省エネ法の対象になります。 設計期間を考えると、2024年12月以降に請負契約を締結するとなると、改正法に対応する必要があるのです。
参考までに、現在の建築基準法における建築物は、震災によりどの程度倒壊するか?も調べてみました。
2000年以降の新耐震基準に基づく建築物の倒壊率は、なんと0.7%。(国土交通省:令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会:委員長=中埜良昭 ・ 東京大学生産技術研究所教授)
最新基準の改正建築基準法・建築物省エネ法に基づく建築物を建てるにあたっては、地震による倒壊も極めて少ないし、住んでからの光熱費も削減できそうですが、建物価格はそれなりに大きく上昇してしまうことは覚悟しなければなりません。
2025年4月1日以降の着工は改正法対応が必須!

2025年3月31日までに着工できるとして、現行基準で行政に建築確認申請を提出しても、引き渡し時には既存不適格といって引渡し時の建築基準法に適合していない建物になります。
たとえば準防火地域で既存不適格の外壁にしてしまうと、そのときの法律に適合していない建物であると判断されることから、将来の売却時に売却が難しくなる=資産価値が失われるという懸念があります。
リフォームであれば主要構造部の過半にあたらない計画にすることで、 建築確認申請をせずに済ませる方法や改正建築基準法で建築確認申請の必要がない建物(新3号特例)にする方法もありますが、 建築確認申請が必要か不要かという判断は、各自治体の判断に委ねられる可能性が高いことから、 計画内容や申請の時期によって各自治体の判断がブレる可能性も否定できません。
審査の長期化で、工期が延長するのは避けられない?
2024年度内に建築請負契約を締結しても、契約後に仕様がなかなか確定できない場合、 2025年4月1日以降の着工になる可能性がありえます。

リフォームの場合、 特に新3号特例の解釈にあたり構造部分の判定基準が明確になるまで時間がかかる可能性を踏まえると、 審査の所要期間は間違いなく確認審査の法定審査期間にあたる35日以内では済まない可能性があります。(設計図書の補正等にかかる期間は法定審査期間に算入されません)
その場合、 改正建築基準法・建築物省エネ法に適合するために建築資材を変更すると、ほぼ間違いなく請負価格が上昇します。
請負契約約款には、請負金額に関する条文があることが想定できるので、請負価格の増額は避けることができません。確認申請にかかる費用は規模などによって大きく変わりますが、目安として新築・リフォームともにおおよそ100万円以上は見込んでおいたほうが良いでしょう。
同様に工期延長に関する条文が入っているケースもありますので、注意するようにしましょう。
工期延長リスクは住宅ローン減税にも影響
工期延長によるリスクは、 たとえば賃貸住宅において客付けと入居が遅れるというリスクはもちろんのこと、 中古住宅においては住宅ローン減税を受けられない、という深刻なリスクが発生する懸念があります。

現在は築年数要件の緩和により、住宅ローン控除が適用となる物件が増え、中古住宅購入の間口が広がりましたが、 住宅ローンを利用して中古住宅を購入する場合、耐震基準適合証明書などが必要であるほか、「中古住宅の取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。*」とは、すなわち決済から半年以内の入居が要件です。
*国税庁タックスアンサーNo.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)に記載。
よって、旧耐震基準の中古住宅を購入してリノベする場合、確認申請が下りるまでの期間が延びてしまうと住宅ローン減税を受けられなくなる可能性があります。
確認申請が下りるまでの期間を短くする目的で、とりあえず申請して指摘されたら直そうとした場合、混乱は増すばかり。結果として6ヶ月以内の入居が叶わなくなります。
たとえ建築確認の遅延リスクについて事前に説明をうけていたとしても、住宅ローン減税が適用されないとなった場合、減税分のアテが外れるダメージは想像以上に大きなものです。
そんな失敗を少しでも軽減するためにも、中古マンション購入×リフォームには専門家を見方に付けて進めましょう!
新3号特例の検討にあたっては細心の注意が必要

2025年4月からの改正建築基準法で定められた新三号特例とは、建築確認・完了検査において小規模建築物(新3号建築物)の一部の規定の審査 ・ 検査が省略される制度のことです。
審査の特例については、法第6条の4第1項 第3号に、検査の特例については、法第7条の5に規定されています。
リフォームご検討中のみなさまにおいては、新3号特例により確認申請なしで工事ができるのではないか? とお考えになる方々も多いかとかと思いますが、 新3号特例適用にあたり勘違いされやすいポイントがあります。
<新3号特例適用の注意点>
規定の審査 ・ 検査が省略されるだけで、 規定の適用は免除されない。
新3号特例対象の木造建築物は次の【いずれか】に該当する木造建築物
1.階数1 2.延べ面積 200m2 以下 3.設計士が設計していること。
建築物の用途 ・ 建築場所によって省略できる規定が異なる。
法第20条の構造(構造耐力)関係の規定については、 全ての新3号建築物に適用できるわけではない。*
*【条件1】通常の仕様規定を満たす(法第20条第1項第4号イを適用する)建築物
【条件2】「特殊な構造方法(令第80条の2)」については、構造方法がプレストレストコンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、型枠壁工法・木質プレハブ工法、アルミニウム合金造で各告示仕様規定部分を満たす構造であること。
よって、新3号特例により確認申請不要といったことではありません。
建築確認申請がなければ、建築確認申請にかかる費用も節約できるかも、とお考えになるかもしれませんが、この点についての【法の抜け道】はそう簡単に見つかるものではなさそうです。実際に住宅会社・リフォーム会社の方々による現地調査がない限り、そう簡単に判断できるものではありません。
つまり。リフォームをご検討中のみなさまにおいては、住宅会社・リフォーム会社の方々による綿密な現地調査がいままで以上に重要になるということなのです。
家づくり・リフォームの進め方をプロに相談したい方はこちらから▼
関連記事
- 憧れのマイホームの総支払額を抑え高コスパ住宅を実現する14+1の方法を大解説!
- 世帯年収1,300万円以上の住宅ローン借入可能額は?実現できる注文住宅の間取り
- 《子育てグリーン住宅支援事業》新築最大160万円!高額になる建築費でペイできるのか!?
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

 注文住宅のハウスネットギャラリー
注文住宅のハウスネットギャラリー