住宅関連記事・ノウハウ
![]() 2025年1月21日(火)
2025年1月21日(火)
 「セカンドハウスの魅力」都会と田舎で二地域居住はメリット以外に、維持費や実現する上での土地選びに注意!
「セカンドハウスの魅力」都会と田舎で二地域居住はメリット以外に、維持費や実現する上での土地選びに注意!
コロナ禍をきっかけに、リモートワークやオンライン会議が当たり前になりました。生活スタイルの変化をきっかけに、日々の生活コストがかさむ都会で暮らすだけではなく、生活コストが少なく済む『郊外』・『田舎』でも暮らす『二地域居住』・『ワーケーション』を実施する方々が増えています。それにあわせて、セカンドハウスや別荘を建てて週の半分を郊外で過ごすライフスタイルが定着しつつあります。ここでは、セカンドハウスのメリットとデメリットだけでなく、理想のセカンドハウスを手に入れるための土地選びやセカンドハウスで使える住宅ローンについて解説していきます。

セカンドハウスとは?
セカンドハウスの定義

セカンドハウスとは、自宅とは別の『居住するための住まい』です。別荘とは、『特別なときにしか居住しない住まい』。セカンドハウスでは『居住するための住まい』として、最低でも月に1日以上は居住しなければなりません。
たとえば、自宅から職場まで行くのに片道2時間以上かかる地域に住んでおり、通勤がたいへんな状況を改善するため職場の近くに住居を購入したとします。このような場合は、生活必需品である居住用財産として判断されます。つまり、セカンドハウスの条件は「最低でも月に1日以上は居住すること」「生活必需品として活用すること」の2つ。どちらかひとつをクリアすれば、居住用財産として認められることでしょう。
セカンドハウスと別荘の違いとは?
別荘の定義

セカンドハウスの条件とは、先に述べた「最低でも月に1日以上は居住すること」「生活必需品として活用すること」の2つ。一方、別荘とは日常生活を過ごすための住居ではなく避暑や避寒といった保養のために利用する住居のこと。別荘は保養施設に分類され「休養のために利用すること」だと考えられています。
セカンドハウスと別荘の違い
以下、セカンドハウスと別荘の違いを簡単にまとめてみます。
- <セカンドハウス>
利用目的:生活 分類:居住用財産 - <別荘>
利用目的:保養 分類:保養施設
税制の違い
セカンドハウスは自宅とは別の『居住する住まい』につき、セカンドハウスを所有する場合、税制面においてさまざまな優遇措置を受けられます。ただし、税の優遇措置をうけるにあたってはセカンドハウスを居住用財産として認めてもらう必要があります。そのため、月に1度以上宿泊して、住居として利用していることを証明する必要があるのです。
セカンドハウスのメリットは「優遇税制」「資産になる」「ライフスタイルの充実」の3つ
セカンドハウスの3つのメリット
セカンドハウスのメリットとして、以下の3つのメリットが挙げられます。

優遇税制について
セカンドハウスとして認められた住居を所有すると、税制面においてさまざまな優遇措置を受けられます。具体的には、固定資産税と都市計画税、不動産取得税の優遇です。
固定資産税の優遇
住居などの物件を所有すると、必ず固定資産税が課せられます。固定資産税の計算方法は「課税標準額(固定資産税評価額をもとに算出される価格)×1.4%」というのが基本。しかし、セカンドハウスは「物件の面積」によって課税標準額に対する税率が決まります。具体的には、200m2未満の物件は課税標準額の1/6に優遇。それ以上の物件は、課税標準額の1/3に優遇されます。
都市計画税の優遇
市街化区域にて住居をはじめとする物件を購入すると、都市計画税が課税されます。都市計画税の計算方法は「課税標準額×制限税率 0.3%」(※税率は市町村の自主的判断)というのが基本。しかしセカンドハウスは、固定資産税と同様に課税標準額に対する税率が「物件の面積」によって決まります。具体的には200m2未満の物件は課税標準額の1/3に優遇、それ以上の物件は課税標準額の2/3に優遇されます。
不動産取得税の優遇
住居をはじめとする物件を購入すると、不動産取得税が課税されます。その計算方法は「固定資産税評価額×3%~4%(土地・家屋(住宅)なら3%・家屋(非住宅)なら4%)」というのが基本。セカンドハウスは計算方法が異なり、住居は「(固定資産税評価額-控除額)×3%」。土地は、計算式が「(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額」になります。
資産価値について
立地条件によって大きく左右されますが、セカンドハウスも立派な資産。居住・賃貸・売却といった有効活用ができるので、将来に向けたストック資産として活用できるでしょう。
ライフスタイルについて
郊外にセカンドハウスがあると、これまでとは異なる休日を過ごすことができます。郊外にあるセカンドハウスで休日を過ごすことができるなら、職場と距離を置けることから心身ともにリラックスできます。また、好きなだけ趣味を楽しんだり自然を感じたりして過ごせることから、完全に仕事を忘れるようなライフスタイルを実現させやすくなるでしょう。
セカンドハウスのデメリットは「維持費」「定期利用が条件」の2つ
維持費がかかる

もちろんのことですが、住宅は定期的なメンテナンスが欠かせません。戸建住宅の維持費は、平均して20年間で500万円程度。つまり1年あたり25万円、1か月あたり2万円以上をみておく必要があります。固定資産税は建物の立地条件によって異なりますが、おおよそ20年で200万円前後が目安。つまり建物メンテナンス費用として20年で300万円程度はかかると想定しておく必要があります。セカンドハウスでも自宅とほぼ同じ程度の維持費がかかると考えると、あらかじめ2棟あわせて20年で 1,000万円程度の維持費をみておく必要があります。また、セカンドハウスを頻繁に利用する場合は、電気代や水道代、ガス代はもちろん、移動にかかる交通費もかかります。そのため、セカンドハウスを維持するには、自宅だけ1棟所有する場合の倍以上の維持費も考慮した見通しを立てておくことが重要になります。
定期的な利用の必要性
セカンドハウス(居住用財産)として優遇税制の対象となるには、最低でも月に1日以上は居住しなければなりません。そのため、セカンドハウスを所有したら「毎週末に居住する」など、定期的に利用する必要があります。
憧れのセカンドハウスの実際の事例を2件ご紹介
セカンドハウス事例
どんなセカンドハウスを建てたいかは、実際に建てた事例を見てイメージをふくらませることが大切です。ご自分の要望を住宅会社に伝える際にも役立つので、ぜひイメージを探してみてください。ここでは、2件の事例をご紹介します。
週末過ごす伊豆高原の平屋セカンドハウス

和瓦葺きの切妻屋根の純和風の平屋。廊下のないコンパクトな間取り、建具も引き戸が多く将来的に移住してきた際の使い勝手も考慮されているそうです。優しい木の風合いで静かに過ごせる落着きある理想的なセカンドハウスです。
趣味のサーフィン・サイクリングのためのセカンドハウス

建物で中庭も囲まれたプライベートをしっかり確保しつつ、趣味に必要な空間も確保し、LDKから続くウッドデッキの深い軒で開放感もありながら実用的で、目的のしっかりとしたセカンドハウスで大変参考になります。
理想のセカンドハウスは土地選びから重要
土地選びのポイント

理想のセカンドハウスを建てるにあたり、どんな土地を選ぶかがたいへん重要です。土地の景観やロケーションは土地によって大きく左右され、自分好みのかたちに変えようがありません。建物の間取りや外観、インテリアについてはある程度の融通は効きますが、土地の特性は変えようがないだけに、その土地の特性をしっかり見きわめる必要があるのです。そこで、どのような土地が良いのか条件を考えましょう。海沿いの開けた景色が良いのか、四季を通じて山の中に篭るイメージが良いのか、自宅からの移動がたいへんではないか、など。そして気になる条件の土地を見つけたら、実際の候補地に足を運ぶことでその土地ならではの様々な条件から優先順位が明確になります。また、土地選びにあたっては、建ぺい率・容積率をはじめとする法律上の制限から、自分たちが理想とする建物を建てられない場合も少なからずあるため事前にチェックしておくことも重要です。そのため、土地選びの段階から気になる住宅会社や建築家など建築のプロに相談することで、その土地ではどんな家が建つのかといった相談はもちろん、その土地では希望に沿った設計が難しいという場合も、土地の検討段階から確認できることから、理想のセカンドハウスのイメージに沿った土地選びを進めることができます。
建築のプロに相談するメリット
土地選びの段階から建築のプロに相談する一番のメリットは、土地の特性による追加コストの予測ができるからです。例えば、海の近くであれば塩害対策は必須だったり、豪雪地帯では構造はもちろん豪雪に備えた屋根や融雪設備の設置も考慮する必要があります。傾斜地ではその地形に合った基礎が必要といった、その土地の特性によって発生する追加コストの想定ができます。事前に追加コストも見越して土地を購入することができれは、設計段階で思わぬ費用が発生して予算オーバーになってしまう事態を防ぐことができます。
地盤やハザードマップの確認
可能であれは、あらかじめ近隣の地盤の状態はもちろん、洪水ハザードマップの確認や土砂災害警戒区域マップの確認といった、行政からの注意喚起情報も把握しておくと良いでしょう。
実際に候補地にあわせて敷地の調査や簡単なスケッチや図面を作成してくれる住宅会社・建築家もいるので、より具体的なイメージをもって土地を選ぶことができることも大きなメリットといえるでしょう。
セカンドハウスを所有する場合の「住民票」と「車庫証明」について
住民票について

これまでセカンドハウスの魅力や成功させる秘訣をご紹介してきました。ここでは、所有した場合に知っておくべき、「住民票」と「車庫証明」について簡単に解説します。ふだん過ごす自宅がある地域に住民票があるのであれば、セカンドハウスがある地域に住民票を移動させる必要はありません。ただ生活拠点をセカンドハウスにする場合は、セカンドハウスがある地域に住民票を移す必要があります。
車庫証明について
自動車を購入、または主たる保管場所を移転する場合、所轄の警察署で車庫証明(自動車保管場所証明書)を発行してもらう必要があります。メインで過ごす自宅で使っている車をそのままセカンドハウスでも使用したいという場合も、基本的には同様の手順を踏みます。ただし、車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要な理由を記した理由書やセカンドハウスの住所が分かる書類等の提示を求められることがあるため前もって準備しておくことが大切です。ただしセカンドハウスとしてお住まいになる自治体によっては、車庫証明(自動車保管場所証明書)が不要な場合もあります。それほど複雑な手続きではないので、ご自身で取得してみることをお勧めします。
セカンドハウスローンで知っておくべき5つのポイント
セカンドハウスローンとは
セカンドハウスローンとは、主として過ごしている住居とは別に、第二の住居を購入する際に組むことができるローンを指します。セカンドハウスローンと通常の住宅ローンの最大の違いとは、セカンドハウスローンが第二の住居を購入する際に組めるローンであるのに対し、通常の住宅ローンは主に過ごす住居を購入する際に組めるローンです。別荘でも利用できるセカンドハウスローンは、家財道具はもちろん既存の住宅ローンとあわせての借り換えなど、柔軟な対応ができる金融機関もあります。ここでは、セカンドハウスローンで知っておきたい5つのポイントを解説します。
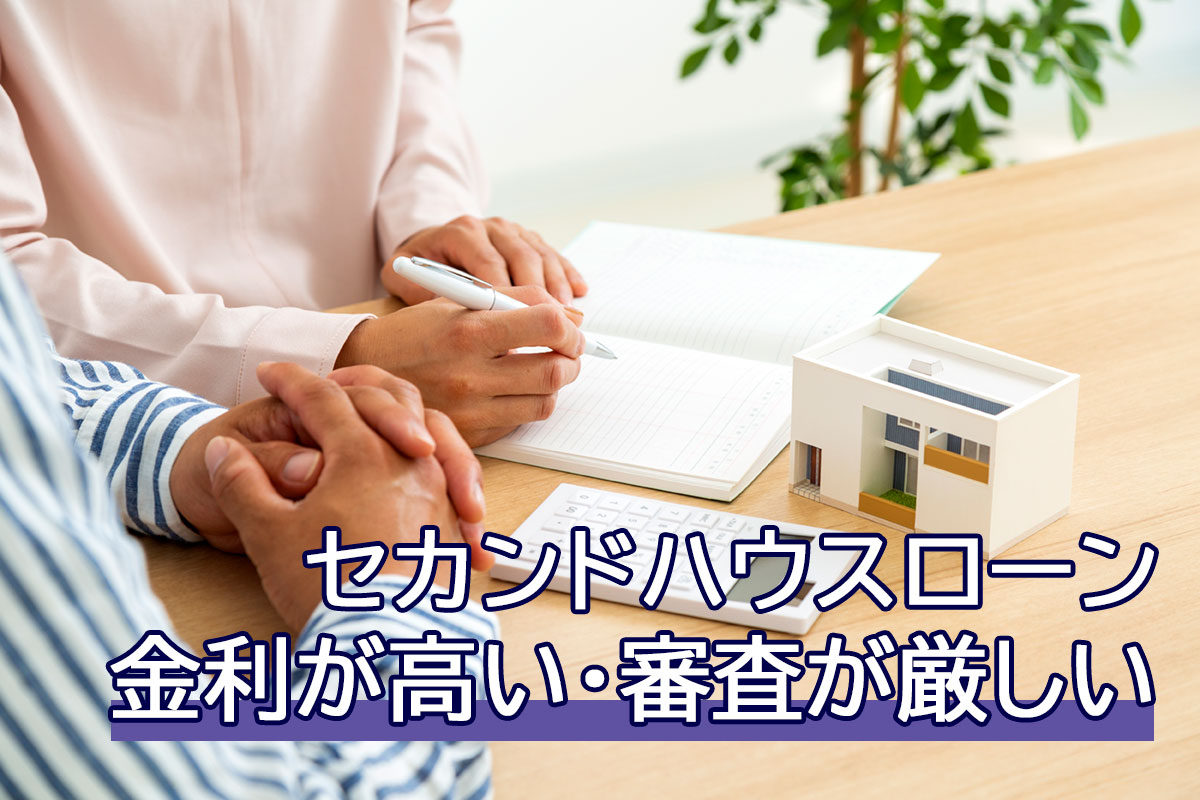
金利が高い
具体的には、一般の住宅ローンと比較して変動金利を選択しても、通常の住宅ローンより金利が0.5%以上高く、かつ審査も厳しくなります。セカンドハウスローンを組む際、実際に返済計画のシミュレーションをして現実的に利用可能かどうか、しっかり検討しましょう。なおセカンドハウスにおける住宅ローン控除は『自己の居住の用に供した』ローンではないことから、住宅ローン控除適用の対象にはなりません。
審査が厳しい
セカンドハウスローンの審査において最も重視されるのは「返済能力」「雇用状況」「健康状態」の3つです。そのため、すでに通常の住宅ローンを組んでおり、追加でセカンドハウスローンを組む場合、一定基準以上の収入もしくは不動産などの担保評価がないと「返済能力がない」と判断される可能性が高くなり、結果として審査に落ちてしまいます。
フラット35の利用も検討
セカンドハウスローンを組むとなると住宅ローンの選択肢が少なくなり、金利はもちろん諸経費も重複するため、住宅ローン利用にあたって出費がかさんでしまいます。そこで出費を最小限に抑えたい場合、民間のセカンドハウスローンではなく【フラット35】を選択するのも方6法のひとつです。
【フラット35】セカンドハウスローンの魅力
【フラット35】は、セカンドハウスの住宅ローンでも通常の【フラット35】でも、どちらも同じ金利です。話題の【フラット35】子育てプラス(S)の金利優遇も使えます。【フラット35】の返済期間は35年、現在の金利は全期間固定金利で年利 2.0%を切る金融機関がほとんど。最大 8,000万円までの融資が可能で、場合によっては団体信用生命保険の付保を外す(金利が 0.2%下がります)こともできます。繰り返しになりますが、民間金融機関が提供している金利に関しては、セカンドハウスローンのほうが変動金利でも0.5%ほど高いため、【フラット35】を利用すれば、さほど大きな金利差にならずセカンドハウスを購入できる可能性があります。
総返済負担率に注意
セカンドハウスで住宅ローンを利用する場合、総返済負担率の上限に配慮しなければなりません。総返済負担率とは、収入に対するローンの返済額の割合。この総返済負担率は、住宅ローン以外にマイカーローンや教育ローン、スマートフォン分割払いなどの借り入れ、クレジットカード利用可能限度額の合計が含まれます。仮にこの基準を上回った場合「長期に渡って無理なく返済するのは困難」と判断され、新たなローンを組めなくなる可能性が高くなります。総返済負担率の上限を上回らないか確認すると同時に、無理なく返済できるような計画を立てることが大切です。なお【フラット35】では、これを「年収が 400万円未満なら30%」、「年収が 400万円以上なら35%」と定めています。この年収に占める総返済負担率の割合が一定の割合を超えると、ローン審査は通りません。
金融機関に確認を
金融機関によって【フラット35】セカンドハウスローンの取扱がない場合もあるので注意。あらかじめ借り入れを検討している金融機関で利用できるかどうか確認しておきましょう。
セカンドハウスはライフスタイル充実の反面、ローンなどの注意点も理解した上で計画しましょう。
セカンドハウスのメリット・デメリットを理解する

セカンドハウスは、自宅とは別の居住するための住まい。セカンドハウスを所有すれば、優遇税制を受けられるほか、資産としての有効活用はもちろん、通勤の利便性が向上したりライフスタイルを充実に役立つなど複数のメリットがあります。ただし、セカンドハウスを購入するにあたって新たに住宅ローンを組むことも多いことから、あらかじめ民間金融機関のセカンドハウスローンの特徴や【フラット35】について理解を深める必要があります。特にセカンドハウスの住宅ローンについては、各金融機関とも一般の住宅ローンと違って充実したメニューや魅力的な金利条件を提示しているわけではありません。セカンドハウスにおける住宅ローンの理解を深めることに手間を感じるかもしれませんが、ここを徹底することで、理想のセカンドハウスを所有したライフスタイルを無理なく実現することができます。セカンドハウスの所有をご検討中の方は、住まいの相談窓口としてプロに相談できるハウスネットギャラリーへぜひ一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
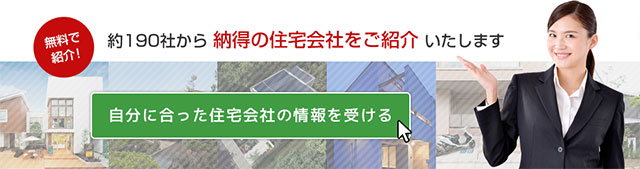
関連記事
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

 注文住宅のハウスネットギャラリー
注文住宅のハウスネットギャラリー






























