住宅関連記事・ノウハウ
![]() 2025年4月1日(火)
2025年4月1日(火)
 注文住宅でよくある後悔15選を間取り・費用・デザイン設計別に紹介
注文住宅でよくある後悔15選を間取り・費用・デザイン設計別に紹介
注文住宅購入の流れと期間:資金計画から住宅ローンまで徹底解説

注文住宅を建ててみたいけど、
- ・何から始めたらいいのかわからない
- ・どのくらいの期間かかるのかわからない
- ・ローンの組み方がわからない
- ・どういう流れで購入すれば良いかわからない
などこのような悩みがある人は多いのではないでしょうか?
重要なのは「どのような暮らしをしたいか」をイメージすることです。今生活している中で不便なことやもう少しこうしたいが、間取りや場所を変えることはできないので難しいことを注文住宅を建てることによって改善できます。
そんな夢のある注文住宅を建てるには、依頼する建築会社や希望の間取りによって異なりますが、家が完成して住み始めるまでにはとても時間がかかり大変です。また、土地から探すとなるとかなり大変な道のりになるでしょう。
しかし、事前に下調べを行い流れが大体わかっていれば入居までスムーズに進めることができます。
この記事では注文住宅購入の流れと期間、支払いスケジュールや住宅ローンの組み方を解説していきます。
購入までの流れや期間を把握すると同時に、建築会社と納得できるまで相談をして理想の注文住宅を建てられるようにしましょう!
注文住宅購入の流れと期間

注文住宅購入を検討してから完成・引き渡しまでは約9ヵ月〜1年半弱かかります。
注文住宅を購入するにあたって、ハウスメーカーや工務店に依頼した場合、大きく分けると次の9つのステップに分かれます。
| 注文住宅購入までの流れ | 期間の目安 | |
|---|---|---|
| STEP1 | 希望条件の整理 | 約2~3ヵ月 |
| STEP2 | 予算検討 | |
| STEP3 | 建築会社の選定 | |
| STEP4 | 土地探し | |
| STEP5 | 土地の売買契約 | |
| STEP6 | 見積もり提示・仮契約 | |
| STEP7 | 工事請負契約 | 約3~4ヵ月 |
| STEP8 | 打合せ | |
| STEP9 | 着工 | 約4~6ヵ月 |
※住宅金融支援機構「2021年度フラット35利用者調査」より作成
希望条件の整理から見積もり提示まで約2〜3ヵ月、工事請負契約と建物の詳細打合せで約3〜4ヵ月、注文住宅の着工から引き渡しに約4〜6ヵ月かかることが一般的です。
あくまでこの期間は目安になりますので、希望するデザインにするために打合せが増えて期間が長くなる可能性もあります。なので、余裕を持ったスケジュール調整を行うのが好ましいでしょう。
ここからは、一つ一つのステップについて詳細に解説していきます。
希望条件の整理
まずは、自分が住みたいと思う注文住宅の希望条件の整理を行いましょう。
家を建てる場所や間取りなど些細なことでも良いので、自分の希望をリストアップすることが大切です。建築会社に相談する際に自分の想像するイメージや希望条件をある程度決めておいた方がスムーズに話が進みます。
希望条件といっても様々ですが、以下の3点を意識して考えましょう。
- ・家の外観・内観や家の間取りのイメージを持つ
- ・住みたいエリアや通勤・通学の時間などを調べておく
- ・自分がこだわりたいものを明確にしておく
間取りやこだわりたいものなどを考える際に注意しておきたいのが、「どのくらい必要なのか」の優先順位をつけることです。自分の希望するイメージが具現化できることが注文住宅の良い点ですが、あまりにもオプションを付けるとその分予算が必要となります。自分の中で「必ず必要なもの」と「あったら便利」の2つに分けて考えることで予算が膨大にならずにうまくまとまるでしょう。
また、実際に建てられている注文住宅の参考資料を見たり住宅街を散歩したりすることで自分の中でイメージを固めていくのも良いでしょう。今の住まいで不満に思っていることを改善するように考えるのもおすすめです。
予算検討
予算検討は注文住宅を建てるうえで1番重要なステップです。予算をある程度考えていないと、後々の住宅ローンの資金繰りやローン返済に苦戦してしまうのでしっかりと考えましょう。
注文住宅を建てるにあたって必要となる費用は、
- 本体工事費:家の外観や部屋を作る費用
- その他工事費:電気・水道・ガスなど生活に必要な設備の費用
- 諸費用:物件を所有する際の登記に必要な費用など
が必要となります。
本体工事費には仮設、基礎、屋根、内装、仕上げなどの費用が含まれます。一番予算がかかるところなので、自分の予算内に収まるように考えましょう。
その他工事費には外構工事、地盤改良などの費用が含まれます。こちらはハウスメーカーや建築会社によって必要な予算が異なるため、事前に相談しておきましょう。
例えば3,000万円の注文住宅を建てるとすると、本体工事費が2,100万、その他工事費が600万、諸費用が300万かかることを目安にしましょう。
大体の人が金融機関で住宅ローンを申し込み、そこからこれらの費用を支払いしていきます。住宅ローンについては後述の「住宅ローンの組み方」にて詳しく解説します。
本体工事費をなるべく抑えたい場合は以下の点を意識しましょう。
- 複雑な形状の家や屋根にしない
- 使う資材や設備のグレードを厳選する
- 水回りの部屋は近づける
これ以外にも造り付け家具や湿式工事を避ける、セミオーダーの規格住宅も検討するなど様々なコスト減少の策はあるので自分で必要なものを取捨選択しましょう。
建築会社の選定
理想の注文住宅を建てるためには、相性の良い建築会社の選定が欠かせません。
例えば、ハウスメーカーを選ぶ際に以下の点を参考に決めましょう。
- 品質:お客様に合わせた、高品質で住み心地の良い注文住宅になるように提案してくれることが大切です。
- プレゼン力:自分の希望する注文住宅になるべく添えるような設計をしてくれる、住みやすい間取りやデザインにもこだわりがあることが重要でしょう。
- コスト面:自分の予想する予算内に収まるのかを考えなくてはいけません。後々、メンテナンスの必要のない素材や建材にもこだわることもよいでしょう。
ハウスメーカーを選ぶ際には、それぞれのハウスメーカーの特徴などを比較・検討することが大切です。どう比較すればいいのかわからない時には各ハウスメーカーのモデルハウスを見に行きましょう。
明確なイメージが固まっていている人は好みのハウスメーカーのモデルハウスに行くのも良いですが、総合住宅展示場に行けば複数のハウスメーカーが展示をしているので様々なメーカーの特徴が体感できるので良いでしょう。
しかし、展示されているカタログなどを隅々まで集めて様々なハウスメーカーに興味を持つことで収集がつかなくなりまとまらなくなってしまう可能性があるので、モデルハウスを見に行くのは自分の中で優先順位を決めて整理してから行くのをおすすめします。
土地探し
土地探しは建築会社の選定と同時に行うことが大切です。
土地選びはそれぞれ判断基準が違うので、以下の基準を参考に何処に重きを置くかをあらかじめ決めておきましょう。
- 土地の大きさ
一番重要なのは土地の大きさです。自分の希望する注文住宅が建てられるかどうかの広さや、家を建てた後車や自転車などの置き場を含めた広さを考える必要があります。 - 交通の便、アクセス(駅から〇〇分)
普段電車やバスを使用し通勤・通学をしなければいけない場合には駅からのアクセスも大切です。しかし、アクセスを良くしても大通りや踏切の近くだと夜間の音がどこまで響くのか等の問題も考えなくてはいけません。 - 日当たり、周囲の建物の状況
日当たりや周囲の建物の状況も確認しておく必要があるでしょう。土地は良くても周囲の物件の高さが高く、日当たりが悪くなってしまうこともあります。また、周りが和風建築なのに対し、希望する注文住宅が北欧風だと一軒だけ浮いた街並みになってしまうので周りの建物の状況の確認も必要でしょう。 - 地盤の強さ、災害時の浸水状況
自然災害の多い日本では災害に強い土地を探すことも重要です。景色を重視した結果、海辺や山奥の土地にするのも良いですがその際は浸水地域などのハザードマップ情報も参考に災害時の対策も必須です。
ただし、すべての条件を満たす完璧な土地を見つけるのはかなり困難でしょう。少しでも良いと思った土地があればハウスメーカーに相談してデメリットをカバーできる間取りしてもらうことも視野に入れましょう。
また、注意点として法規制と建築条件付き土地があります。
法規制によって家を建てられる土地なのか、どのくらいの大きさまでの建物なら建てられるのか、水道・下水・ガスによって購入費用とは別に費用がかかるのかどうかを確認する必要があります。
建築条件付き土地とは販売元の建築会社で家を建てることを条件に土地を販売するというものです。
この注意点として、途中で建築会社を変更できず変えるには違約金が必要になってしまうことや間取りや建築プランが制限されてしまうことがあるので注意しましょう。
土地の売買契約
土地購入の流れは大きく分けて3つのステップに分けられます。
- 買付証明書の提出
- 土地売買条約
- 引き渡し
1.買付証明書の提出
説明を受け、双方納得がいけば売買契約書に署名し契約締結となります。気に入った土地があればまず、購入の意思を表す「買付証明書」を提出する必要があります。これは基本不動産会社から渡される専用の用紙に買主の署名や押印を行うもので、売主が条件に納得すれば契約が進むことになります。買付証明書は購入の申し込みを行うものなので、金銭の取り扱いは無く撤回料などの違約金も発生はしません。
また、自己資金で購入する場合はこのまま土地売買に進むことができますが、大半の人は住宅ローンを組むこととなるでしょう。買付証明書提出の前後で事前審査を行っていないと契約までに間に合わない可能性があるので、余裕があるうちに住宅ローンの事前審査を通しておきましょう。
2.土地売買契約
契約時には土地代の約10%を手付金として現金で払う必要があります。また、重要事項の説明として今まで紹介されたり紹介されたりした情報の最終チェックがあるので自分の希望と異なる場合や不明な点がある場合は申しつけましょう。
住宅ローンの審査が通らなかった場合や契約の内容不備による契約解除の時の対応など最悪なケースも説明があるのでしっかりと確認しておきましょう。
3.引き渡し
売買契約が締結したら次は引き渡しになります。あとは残金の支払いを行うために売主の口座に残金を振り込む手続きを行います。これが終われば土地が自分のものとなります。
土地売買から引き渡しまでは基本1〜2ヵ月かかるので、ことがスムーズに進むように必要な書類などは用意しておくことが望ましいでしょう。
見積もり提示・仮契約
モデルハウスなどを見に行き、自分の建てたいと思う注文住宅の雰囲気に合う建築会社を厳選したら各建築会社ごとに以下の3点を依頼し、作成を依頼しましょう。
- 簡単な部屋の間取り図
- 見積もりの概算
- 資金計画書
特に自分の望む間取りやこだわりポイントを重要視して伝えることを意識しましょう。ここで自分の想像するイメージがうまく伝えられないと、後々の打合せにて間取りや予算がかけ離れてしまうことがあるので注意しましょう。希望する間取りや詳細設備などを明確にしておけば見積もり作成もスムーズに進むでしょう。
また、建築会社を決めるうえで以下のことを意識しながら比較しましょう。
- 間取りの提案力:自分のイメージ通りの間取りになっているか
- 建物のデザイン性、構造:好みの外観、耐震・遮音・断熱性に問題はないか
- 見積もり額:想像の予算に合っているか
- サービス体制:後々の保障・修繕費、担当者が相談しやすいか
作成してもらった見積もりなどから比較し、1番自分の条件に合う建築会社が決まったら仮契約を行い次の工事請負契約(本契約)に進みます。
工事請負契約
これまでの過程を経て、建築会社を1社に決定したら工事請負契約を締結します。
工事請負契約とは別名本契約と呼ばれ、依頼人は注文住宅の完成に対しての代金を支払うことを約束し建築会社は求められた工事を完遂することを約束するものです。
この工事請負契約は仮契約とは違い正式な手続きの為、途中の契約変更やキャンセルによって違約金の支払いを求められるのでしっかりと確認を行い契約を結びましょう。
また、この時点で建築費の約10%の手付金が必要な場合もあるのでその点を含めて金額の支払い時期なども詳細に確認しておきましょう。
打合せ
工事請負契約後、注文住宅を建てるために詳細打合せを行います。
主に以下の点について話し合います。
- 内装、外観のデザイン、住宅設備や建材
- 間取りの詳細
- 住宅ローンの本審査までの流れの確認
- 着工日など工事にかかるまでの日程の確認
- 建築確認申請(建てようとしている家が建築基準法を違反していないか)
もし、建築のプランに変更がある場合は契約変更を行う必要があります。
設備の抜け漏れなどで建築確認の再申請を行わなければいけない際には別途費用がかかり、着工までの期間も長くなるので注意しましょう。
着工
事前準備に何も問題なく進めば、最後に工事の着工にはいります。
着工時に以下のことを進めておくことでこの後の入居までの流れがスムーズになるのでしっかりと行いましょう。
- ご近所の挨拶回り
- 地鎮祭、上棟式の有無の確認
- 引っ越しの準備
- 工事の状況の確認
工事中は業者の邪魔にならない程度に配慮し、進捗状況を確認しに行くことも良いでしょう。時々工事している内容と図面が異なっていないかなども確認しておく方が後々の不満、トラブルを回避できるので重要です。
竣工・引渡し
竣工(建築工事や土木工事が完了すること)して建物が完成したら市区町村による完了検査を受けます。建築確認申請に基づき、建てられているか確認がされた後検査済証が発行されます。
建物の引渡し前には施主の立会いのもと図面通りに建てられているか、目立った汚れや傷が無いかなどを最終チェックします。ここで気になる場所があれば引渡し前に必ず伝えましょう。引渡し後に発覚し指摘した場合、工事費用がかかることがあるので注意しましょう。
特に問題が無く終われば、鍵や保証書を受け取り自分の家となります。
注文住宅の支払いスケジュール
注文住宅を建てるにあたって、どのくらいの費用がかかるのか・支払いのスケジュールがわからなくて心配という人も多いのではないでしょうか?
ここからは記事では注文住宅でかかる費用とスケジュールをまとめて解説します。

注文住宅でかかる費用
以下の3点があります。
- 土地購入費用(土地がある場合は不要)
土地購入費用は主に「手付金」、「仲介手数料」、「固定資産税の日割り分」などを支払うことになります。
手付金は一般的に土地代金の1割、または100万円となっていることが多いです。仲介手数料や固定資産税は建築会社によって異なるので、しっかりと確認しましょう。 - 建築・工事費用
建築・工事費用は以下の4つに分けられます。- 注文住宅契約時:工事代金の約1割を支払います。
- 着工時:工事代金の約3割と地盤調査や建築確認の費用も必要になります。
- 上棟時:工事代金の約3割を支払います。
- 引渡し時:工事代金の約3割と登記、ローン費用が必要になります。
- 諸費用
- 諸費用には引っ越し代金、固定資産税などが含まれます。2、3月は引っ越しの繁忙期になるため、比較的高くなる可能性があるのでその点も考慮しましょう。
- 固定資産税は毎年1月1日に土地を所有している人に課税されるものです。土地を所有している間は毎年納税の義務が課せられるので注意しましょう。
土地代+注文住宅の建設費に必要な費用は全国平均で4,397万円です。首都圏は平均5,162万円となっており、地域によって必要な土地代が異なるのでしっかりと確認することが重要でしょう。
建てる地域によって異なりますが一般的な予算の配分としては、土地購入費用が25%、建築・工事費用が70%、諸費用が5%となっています。土地購入に多くの割合を充て、満足の行く注文住宅を建てる費用が無くならないようにあらかじめ大まかな概算を立てておくことが重要です。
建ててから入居までの支払い回数
具体的に注文住宅を建ててから入居までには3〜4回の支払いがあります。
- 工事請負契約締結時:約10%
- 工事着工時:約30%
- 住宅の骨組み完成時:約30%
- 引渡し時:約30%
建築会社によって支払うタイミングが異なる場合があるので、しっかりと確認しスケジュールを把握しておきましょう。また、土地購入費用と建築・工事費用とは別に「土地の地盤強化」「外構工事」「水道管引き工事」などの諸費用が必要になるのでしっかりと計算に入れておきましょう。
★【関連記事】注文住宅の費用相場はいくら?費用内訳・予算別の特徴も解説!
住宅ローンの組み方

注文住宅を購入するにあたってほとんどの人が住宅ローンを組むことになるでしょう。
住宅ローンを組むには「仮審査」と「本審査」の2種類に通る必要があります。
仮審査とは年収や継続年数、自己資金の割合などがポイントとして審査されます。仮審査を受ける段階では建築会社や間取りなどはまだ本決定する前でかまわないので、提案されている書類を含めて審査にかけます。最近では金融機関の窓口での書類記入だけでなく、インターネットや郵送での手続きもできるので、自分に合うやり方を検討しましょう。
金融機関によって異なりますが仮審査には約1週間程かかるため、土地の売買契約時に仮審査が通っていることが好ましいです。
仮審査が通ったら次は本審査に移ります。
工事請負契約の締結後、詳細な打合せを行う際に本審査を行いましょう。仮審査が通っていても本審査に落ちる可能性があるので、この期間に借入や転職などの収入が不安定になってしまうことにならないようにしましょう。
本審査では詳細の審査を行うため、約2週間ほどかかるので融資が始まるまでの期間をしっかりと考えて行いましょう。
本契約が通れば金融機関と契約締結となります。
また、住宅ローンと併せて「つなぎ融資」を利用する人もいます。
つなぎ融資とは住宅ローンの審査が通るまでに一時的に借入できるローンです。土地を買う時の土地代や、着工時から竣工時までの建築費などの用途で使用する人が多いです。つなぎ融資を利用する方法は、住宅ローンを締結する金融機関にあらかじめ確認することが必要になります。
しかし、住宅ローンより金利が高く、取り扱っている金融機関が少ないため借りないですむならば極力借りなくてよいでしょう。
注文住宅の購入の流れや期間を把握していないと行き当たりばったりの依頼をしてしまい、想定以上に注文住宅が建てるまでの期間が長引いてしまう可能性があります。
あなたがこの時期までには注文住宅を建てたいという希望があるなら、注文住宅の購入の流れや期間を理解するように心がけましょう。
注文住宅の流れや予算などについて、専門家の意見を聞いて進めたいという方は、こちらからどうぞ。
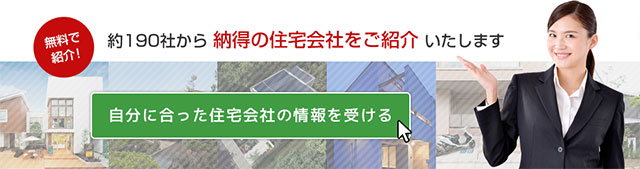
関連記事
- 注文住宅の間取りの決め方は?人気の間取り10選も紹介!
- おしゃれな注文住宅の5つのコツを解説!おしゃれな外観・内観の特徴も紹介
- 2023年の金利上昇に備えた、新しい住宅ローン選びのポイント。変動か固定かしっかり判断しよう!
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

 注文住宅のハウスネットギャラリー
注文住宅のハウスネットギャラリー






























