住宅関連記事・ノウハウ
![]() 2025年4月1日(火)
2025年4月1日(火)
 家を建てるのに必要な費用はいくら?
家を建てるのに必要な費用はいくら?
マイホーム建設費用はいくら?内訳から地域差、税金まで徹底解説

結婚や出産のタイミングで一戸建ての購入を検討する人は多いのではないでしょうか?子ども部屋をいくつ作ろうか、リビングは広い方がいいなど、どんな家にしようか考えるとワクワクします。一方で、夢のマイホームを建てたいけれど、どれくらい費用がかかるのか不安ですよね。
この記事では、
- 家を建てるときに必要な費用の内訳
- 建てる地域による費用の差
- 家を建てたあとにかかる費用や税金
について解説します。
家を建てるために必要な費用にはいくつか種類があります。
実際に「家を建てるのにこんなに費用がかかるなんて知らなかった」「思っていたよりも費用がかかった」と驚く人は多いです。
家は一生に一度の大きな買い物です。費用面が心配でハウスメーカーなどに問い合わせる勇気が出ない人もいるでしょう。この記事を読んで、家を建てるためにどのような費用がかかるのか、また建てたあともどれくらい維持費がかかるのかをしっかりと理解した上で、マイホームを建てるのか検討をしましょう。
家を建てる費用の内訳を知ることで、家を建てるお金の不安は軽減できます。家を建てようか悩んでいるあなたに向けて、わかりやすく解説しているのでぜひ最後まで読んでください。
家を建てる時に必要な費用
家を建てる費用には、土地代や建築費用の他にもさまざまな費用がかかります。
例えば、建物の工事以外にも「ガレージや玄関の門扉の設置などの外構工事」や「エアコン設置」なども家を建てる際に必要な費用です。建築以外の部分で言うと、「住宅ローンを組むための事務手数料」や「印紙代」などの諸費用もかかります。
これらの費用はチラシやネット上の住宅情報には載っておらず、ハウスメーカーなどで詳細の見積もりをとってから気づくパターンがほとんどです。
ここからは、実際に家を建てるときに必要な費用は以下の4種類です。
- 本体工事費用
- 付帯工事費
- 土地代
- 諸費用
それぞれの費用相場や工事や手続き等について紹介します。
家を建てるために、どのような費用がかかるのか1つずつ理解していきましょう。これらを知っておけば、ハウスメーカーの営業文句に乗せられる心配もありません。
本体工事費用
本体工事費用とは、家の建物部分だけの建築費用のことを言います。
ハウスメーカーなどで家を建てる相談をした際に、「坪単価」という家を建てるときの目安となる金額を教えてくれますが、これが本体工事費用に当たります。よく本体工事費用だけを見て、「意外と家を建てるのは安い」と誤解してしまうケースがありますが、注意が必要です。
本体工事費用に含まれる費用は以下のとおりです。なお、ハウスメーカーによって含まれる費用が異なる場合があるため担当者への確認も重要です。
- 仮設工事:足場組みなど建設する準備のための工事
- 基礎工事:家の基礎を作るための工事
- 木工事:大工さんが行う木材や建材などの取り付け工事
- 屋根工事:瓦や板金などで屋根を覆う工事
- 外装工事:外壁の塗装やタイル工事
- 内装工事:壁や天井のクロス張りや畳の設置など
- 建具、住宅設備機器工事:ドアやシステムキッチン、お風呂の設置などの設備工事など
本体工事費用は家を建てるためにかかる総費用の7割〜8割を占めます。本体工事に含まれていない工事はすべて付帯工事になります。
付帯工事費
付帯工事費用とは、建物本体以外にかかる工事費用です。「別途工事費用」と呼ぶ場合もあります。ハウスメーカーで家を建てる場合、付帯工事は専門業者に委託するケースがほとんどです。
付帯工事費用に含まれる費用は以下のとおり。
- 外構、造園工事:門扉やカーポートの設置、庭の植栽など家の外回りの工事
- 引き込み工事:水道やガス、通信回線などを家に引き込む工事
- 地盤改良工事:地盤の強度を高めるための工事
- 解体工事 ※建て替えや古家付きの土地の場合
- 照明器具工事
- カーテン工事
- エアコン設置工事 など
照明器具工事やカーテン工事などの内装工事がなぜ入っているのか気になった方もいるのではないでしょうか?
実は、本体工事費用にはリビングやダイニング、寝室の照明器具やカーテンレールの設置などが含まれていないケースが多いのです。ハウスメーカーによってどこまで本体工事費用に含まれているのか異なるので、見積もりを取った際に確認しておきましょう。
土地代
家を建てるときには、土地を持っておかなければなりません。両親からの贈与や相続で土地を持っている場合は購入の必要はありませんが、多くの人は土地を購入する必要があります。
土地の購入に必要な費用
- ・土地代(手付金を含む)
手付金とは、土地を契約する際に土地代金の一部を先払いするお金です。土地代金の約10%が相場です。 - ・不動産売買契約書への印紙代:約1万〜2万円
- ・仲介手数料:土地代×3%+6万円+消費税
仲介手数料は取引金額に応じて法律で決められています。
例えば、1,000万円の土地を購入する場合の費用
- ・土地代:1,000万円
- ・印紙代:1万円
- ・仲介手数料:36万円+消費税
合計 約1,040万円かかることになります。
土地を購入して家を建てる場合には、土地と建築費用の両方を考える必要があります。
諸費用
諸費用とは、家を建てるためにかかる事務手数料や税金のことを指します。諸費用に含まれる費用は以下のとおり。
- 建築確認申請手数料
建築確認申請とは、新しく家を建てるときに必要な申請で、着工前に設計図などを役所に提出する手続きです。申請するのは家主ですが、ハウスメーカーの担当者が代行することが多いです。 - 登記費用
登記とは、土地や建物の所有を証明するための手続きです。登記の際には登録免許税や不動産取得税の支払いが必要になります。 - 火災保険料
火災保険の加入は義務付けられていませんが、万が一のために加入しておきましょう。日本では地震のリスクもあるため、地震保険にも加入しておくと安心です。 - 住宅ローンの事務手数料
住宅ローンを組む際の手続きにかかる費用で、金額は金融機関によって異なります。 - つなぎ融資費用
つなぎ融資とは、家が完成するまで住宅ローンの融資を受けられないため、それまでの間、一時的に借入する融資のことを言います。家が完成するまでにさまざまな支払いがあるため、その費用の支払いにつなぎ融資を使います。 - 印紙代
不動産の売買契約書には印紙が必ず必要です。その費用も負担することになります。
これらの他に、引越し費用や家具・家電の購入費用などがかかります。諸費用は一度にまとめて払うわけではありませんが、必要なときにその都度支払う必要があります。
建物にかかる費用は地域によって違う?
| 地方 | 住宅面積(m2) | 建築費(万円) |
|---|---|---|
| 全国 | 123.8 | 3,569.7 |
| 北海道 | 123.8 | 3,627.6 |
| 東北 | 135.2 | 3,315.1 |
| 北関東甲信越 | 125.7 | 3,372.1 |
| 南関東 | 124.0 | 3,730.1 |
| 東海 | 124.2 | 3,674.0 |
| 北陸 | 135.0 | 3,628.5 |
| 近畿 | 1247.1 | 3,775.7 |
| 中国 | 119.7 | 3,528.3 |
| 四国 | 115.2 | 3,279.4 |
| 北部九州 | 124.2 | 3,452.2 |
| 南九州 | 115.1 | 3,204.1 |
全国では住宅面積が123.8㎡(約37坪)で建築費が3,569.7万円が平均です。
住宅の広さに違いはありますが南関東や東海、近畿地方の建設費用は他の地域と比べると費用が高い傾向にあります。「2021年度フラット35利用者調査」には、都道府県別のデータも記載されているので自分の家を建てる地域はどれくらい費用がかかるのか気になる人はチェックしてみてください。
家を建てたあとにかかる税金・費用は?
家を建てる人の多くは家を建てるときの費用だけに注目しがちで、そのあとかかってくる維持費まで考えていない人も多くいます。
家を建てたあと、維持していくためにも結構なお金がかかるものです。
税金や保険料、故障したときのメンテナンス代やリフォーム代など、建築費のように一度にかかる費用ではありませんが、毎年支払う必要があったり、突然支払いが必要になったりします。家を建てようと思っているのであれば、建てたあとにかかる費用についてもある程度理解しておきましょう。
ここでは、以下の6点について紹介します。
- ・不動産取得税
- ・固定資産税
- ・都市計画税
- ・火災保険料、地震保険料
- ・家のメンテナンス代
- ・リフォーム代
家の維持費について知ることで、資金計画が立てやすくなります。
不動産取得税
不動産取得税とは、名前のとおり家などの不動産を取得したときにかかる税金です。毎年支払うのではなく、家を建てたとき土地と建物分それぞれ1度だけ支払います。
不動産取得税の計算方法は以下のとおり。
【建物】 不動産取得税=建物の固定資産税評価額×税率4%
【土地】 不動産取得税=土地の固定資産税評価額×税率4%
※固定資産税評価額とは、固定資産税の基準になる評価額のことで、市区町村が算出します。どれくらいか知りたい場合は、土地・建物それぞれの販売価格の70%ほどだと思っておくといいでしょう。
<例>購入価格3,000万円の建物の場合
固定資産税評価額:1,500万〜2,000万円ほど(固定資産税評価額2,000万円として)
不動産取得税:80万円(2,000万円*4%)
納税方法は、家を取得した日から60日以内に都道府県税事務所に納めなければなりません。ただし、自治体によっては支払い期限が異なるので必ず取得した都道府県のHPなどで確認しておきましょう。
固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日時点で家や土地などの不動産を持っている人が各自治体に支払う税金です。
計算式は以下のとおり。
固定資産税=課税標準額×1.4%
※課税標標準額と固定資産税評価額は同額です。
固定資産税は、特例や減額措置によって安くなる場合があり、特に新築の家を建てる場合は優遇されます。
住宅用地の特例
以下に該当する場合は、課税標準額が減額されるため固定資産税が下がります。
| 固定資産税 | |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200m2以下の部分) | 固定資産税 評価額の1/6 |
| その他の住宅用地(200m2超の部分) | 固定資産税 評価額の1/6 |
※居住の用に供する建物が複数ある場合は、小規模住宅用地は棟数分適用されます。例えば、2棟ある場合は最大400平方メートルまで適用されることになります。
新築住宅の軽減措置
2024年3月31日までに新築で建てた家については、一定期間、固定資産税が軽減されます。要件と内容は以下のとおり。
【要件】 居住部分の床面積が50m2以上280m2以下
軽減内容・期間
| 軽減内容 | 期間 | |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅 | 課税床面積が120m2以下の部分につき、固定資産税が1/2に軽減 | 一般の住宅:5年間 3階建て以上の中高層耐火・準耐火住宅(マンションなど):7年間 |
| 上記以外 | 同上 | 一般の住宅:3年間 3階建て以上の中高層耐火・準耐火住宅(マンションなど):5年間 |
※減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけ。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。さらに、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。
認定長期優良住宅とは、災害や住環境への配慮など長期間家を良い状態で使うための措置が行われている住宅のことを言います。項目は5つあり、すべての措置を行い自治体に認定申請を行えば認定を受けられます。
都市計画税
都市計画税とは、インフラ整備や市街地の開発、土地の区画整理などを行うため、市町村に支払う税金です。
市町村はこの費用を使って道路や公園を作ったり、災害対策の施設、都市開発をしたりしています。都市計画税がかかるかどうかは家を建てる場所の自治体によって異なり、現在日本の約1/3の市町村が課税を行っています。家を建てる地域が都市計画税の対象か確認しておきましょう。
計算式は以下のとおり。
都市計画税=固定資産評価額×0.3%
都市計画税についても、固定資産税と同様に特例措置があります。
| 都市計画税の課税標準額 | |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200m2以下の部分) | 評価額の1/3 |
| その他の住宅用地(200m2超の部分) | 評価額の2/3 |
毎年4月〜6月ごろに固定資産税と都市計画税の納税通知が自宅に届きます。支払いは一括でも4期に分割しての支払いでも可能です。
火災保険料、地震保険料
マイホームを建てる場合、火事や災害に備えて火災保険・地震保険に加入するのが一般的です。
火事で家が燃えたり、地震で家が潰れてしまって建物や家電、家具が破損したときに使います。仮住まいや家を建て直し、家具や家電を買い直すには膨大な金額がかかります。
火事や地震がいつ起こるのかわからないため、火災保険や地震保険には必ず加入しておきましょう。
火災保険料は、家を建てる地域や建物の構造、補償内容などさまざまな要素をもとに決まります。
例えば、東京で2023年1月に5年一括払いで面積100㎡の一戸建てを建て、火災補償額2,000万円、補償内容は建物のみ(火災、風災、水災、破損・汚損)で家財補償や地震保険を付保しない場合は以下の内容になります。
価格ドットコム調べ
| 火災保険料 | |
|---|---|
| 木造など(H構造・非耐火) | 約7万円〜12万円 |
| 鉄筋・鉄骨など(T構造・耐火) | 約4万円〜9万円 |
木造住宅(耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火以外)は鉄筋・鉄骨の住宅に比べて燃えやすいという点で、料金が割高に設定されています。上記はあくまでも一例なので、建てる地域や補償内容によって料金は変動します。
家のメンテナンス代
お風呂やトイレなどの水回りが壊れたり、フローリングが傷んでしまったりすると、賃貸とは違い自分で修繕しなければなりません。新築を建てて数年間はメンテナンスの必要のないケースがほとんどですが、築10年を過ぎたぐらいから少しずつ家のメンテナンスが必要になってきます。
メンテナンス費用は住む期間によっても変わりますが、合計約600万〜800万円かかることも珍しくありません。
その中で最も高額になるのが「外壁塗装」です。築10年を超えると外壁が汚れたりひび割れが起きたりします。家の見た目をキレイにし、家を保護する目的で塗り替えが必要です。他にも、キッチンやお風呂、トイレが急に壊れて買い替えが必要なケースもあります。
一戸建てを建てた人の中には、このメンテナンス費用まで考えておらず急に大きな出費が発生して困る人も多いです。新築のうちは必要ありませんが、コツコツ貯めておくといいでしょう。
30年住む前提で修繕費が800万円かかるとすると、1ヶ月約22,000円ずつ貯金しておくと急な出費にも備えられます。
リフォーム代
一戸建てに長く住んでいると住宅の強度が落ちてきたり、家族構成の変化や介護が必要になったりしてリフォームを検討する人もいます。いつかリフォームをするかもしれないと想定しておくことも重要です。
リフォームにかかる費用は、リフォームする場所や内容によって大きく変わります。例えば、室内を部分的にリフォームする場合は最低でも約200万円ほどの費用が必要です。
主なリフォーム費用について
- ・キッチン:50万〜150万円
- ・浴室:50万〜150万円
- ・トイレ:15万〜50万円
- ・洗面所10万〜50万
- ・壁や天井のクロス張り替え:750〜1,500円/㎡
- ・フローリングの張り替え:2万〜6万円/畳
- ・間仕切りやドアの新設・撤去:7万〜35万円 など
築年数が30年を超えると建物や設備が古くなり、リフォームをする人が多いです。メンテナンス費用と同様に少しずつ貯金しておくといいでしょう。
まとめ
この記事では、家を建てるためにかかる費用や地域による建築費用の差、建てたあとにかかる費用について解説しました。家を建てるときには、建物自体の費用以外にも外構費や設備工事費用、手数料などがかかります。ハウスメーカーなどで見積もりをした際にそれらの費用が記載されていないケースもあるので注意が必要です。
見積書を見たときに付帯工事費や諸費用がどれくらいかかるのか質問できると、家を建てるための総費用の目安がわかりやすくなります。
また、家を建てたあとは毎年支払いが必要な税金や急に必要になるメンテナンス費用やリフォーム費用などがあります。
家は建てたら終わりではなく、維持するためのお金も必要です。急な出費に備えて貯金することが重要です。
家を建てるにはお金がかかりますが、どのようなことにお金がかかるのか先に知っておけば、今後のマネープランも立てやすくなります。この記事を読んで、しっかりとお金の準備を進めていきましょう。
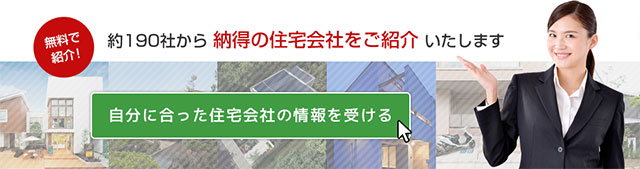
関連記事
- 予算2,000万円からが注文住宅の面白いところ。どんな家が建つ?注意点は?
- 2023年の金利上昇に備えた、新しい住宅ローン選びのポイント。変動か固定かしっかり判断しよう!
- お金がないのに家を建てることは可能?
- 家を建てるタイミングはいつ?家を建てる時期の決め方を解説
- 憧れのマイホームの総支払額を抑え高コスパ住宅を実現する14+1の方法を大解説!
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

 注文住宅のハウスネットギャラリー
注文住宅のハウスネットギャラリー































