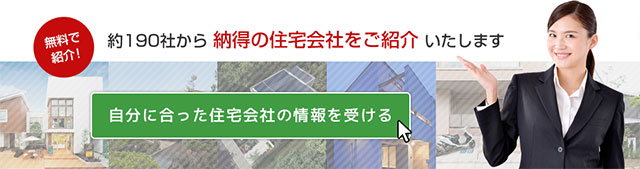住宅関連記事・ノウハウ
![]() 2025年3月31日(月)
2025年3月31日(月)
 「日本は“傘の家”で欧州は“壁の家”?家は命!」
「日本は“傘の家”で欧州は“壁の家”?家は命!」
これからの家は「夏を旨とすべし」の自然住宅
日本の住まいの原点
住まいの設計あたって私がいつも参考にするのは「徒然草」です。日本の住まいや暮らしの原点を知るためにいろいろな古典を読み漁った中で、わが国の偽らざる本音の生活や世相を適格に言い著しているのがこの随筆だと思うのです。
まさしく何百年にもわたって人々が読み継いで来ている事実からみても、それが日本人の生活の知恵として疑わないのです。近年においても鎖国から明治維新、そして戦後と、急激に西洋化され、近代化が進み、今や「衣食住」のすべてが西洋化されハイテク化されているのですが、どれほど西洋化が進もうとも、不思議なことに日常の生活や行事はあい変わらず春夏秋冬のはっきりした四季の折りなしの中で営われているのです。
「衣」の装いも「食」の豊かさも、さらには「住」の設えも、まるでDNAのように根源は日本の古きかたちであり、日本固有の自然である湿気対策の上にすべてが成り立っているように思え、戦後住まいはたちまち西欧化され、次々とコンクリートの集合住宅も建てられ、今や一戸建ても壁式の高気密高断熱で外断熱だ、設備もハイテク化されて、欧米顔負けの素晴らしいインテリアとなっているのですが・・・、なぜか家の中までは絶対に土足の暮らしにはならずいまだスリッパの生活なのです。
生活の中の「衣」・「食」・「住」は誰にとっても大切なことで、大きな楽しみでもあるのです。さらに創造の源であり、文化でもあるのです。しかし今は大量生産と大量販売で、「衣」は既製品やイージーオーダーのものが急激に進化し、「食」も地域の食文化は衰退し、フランチャイジャーとして、ファーストフードはどの街にも存在し、あらゆるものがインスタント食品となり、しかも廉価に入るようになったのです。
「住」においても増改築がリフォームと名を変え、多くの業種が参集し、ついには訪問販売から、詐欺行為の手段とまでなっているのです。こうして日本の「衣食住」はすべてにおいて大量販売のデリバリー商品となったのです。
しかし、その一方で人々の住まいの本質的なニーズは “日本”で、本音では古い民家にあこがれたり、無垢の木や土に親しもうともしているのです。わが国の生活文化はいったいどこへ行ってしまったのだろう?と思いきや、若い人たちは浴衣や着物を好んで着るようになり、健康的な日本料理に人気が集まり、「住」も無垢(むく)だ、手づくりだと、昔の良さに目覚めてか、民家ブームや自然素材の本物思考となっているのです。
住まいはそうした気候と風土の中に息づいていることを感じさせるのです。そのテーマこそ“湿気”です。暑いときも寒いときも常に湿気にかかわり、そしてこの梅雨のときこそわが国の住まいはその本領を発揮してきたのです。ところが諸外国の家の形は歴史を見てもその本質においてさほど変わっていないのです。
これほど根の深い湿気の国でありながら、突如としてその本質の違う工法や材料による壁の家となり、洋風思考や近代化はおろか、住も見事に工業製品となり商品化され、わが国の生活文化として浸透したのです。
この先さらにどうなるかですが・・・すでに高齢者の多くは空調機や除湿器を嫌って、自然の風を求め、自然と調和する生活を求めているのです。
わが国の家の原点は“蓑傘”の傘の家
日本の伝統的な住まいの知恵
いま「衣」・「食」・「住」のすべてが新たな創造へと向いているのです。地球の環境問題だけでなく、誰にとっても自然の恵みは大きな悦びで、創造の源です。やっといま本来の日本の暮らしに回帰しようとしているのです。そして住まいは、やっぱり「夏を旨とすべし」を心得るのです!今回の大震災と原発事故から電気不足が考えられ、いまや住まいは改めて自然との共存を迫られ、風通しを求められ、「夏を旨とすべし」となっているのです!日当たりが欲しい!今流に言えば“日照権”が主張されるのですが・・・実は古来わが国の家はその“日照”なるものを向かい入れる構造ではなかったのです。ほとんどの民家が床をあげ、深く低い庇(ひさし)で、そのうえに縁側なる広縁があり、その奥に部屋があるのです。
明らかに深い軒や庇は日陰をつくり、雨を避け、湿気を嫌って、床を高く上げ風を通し、冷えた空気を室内に取り入れようとする“傘の家”の構造だったのです。
それがやがて街に住むようになり、都市化され、密集化し、幾度かの大火に見舞われると、隣家との間は燃えない防火の土壁で囲い、“傘”を家の中央の中庭に向け、そこに小さな自然と日陰をつくったのです。それこそが今も続く町家です。この1000年、私たちの湿気対策の“傘の家”の文化は一体何が変わったと言うのでしょう戦後のわずか66年の間に変わったことなど、気候風土を原点とする「徒然草」の本質に比べ、本来あるべき姿だったかどうかをこの梅雨の季節が教えてくれるのです。
日本は“傘の家”で欧州は“壁の家”?家は命!
日本の家と西洋の家の違い
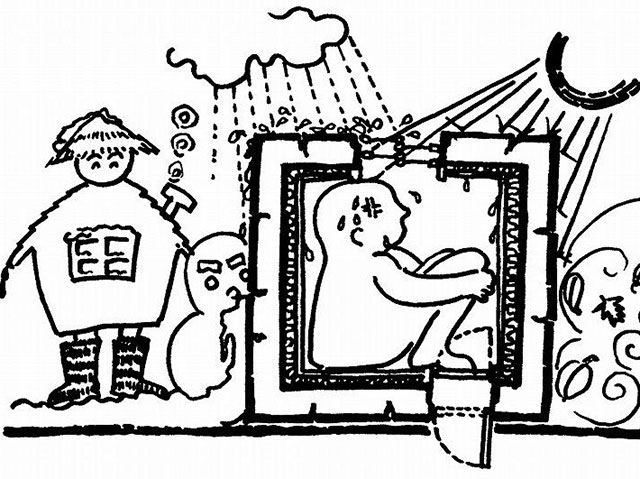
明治140余年、戦後のわずか65年の間に変わったことなど、気候風土を原点とする「徒然草」の本質に比べ。本来あるべき姿ではなかったことを、また、この梅雨から例年になく余りにも暑い季節が教えてくれるのです。
この十数年来アジアを除き、ヨーロッパやアメリカの経済はあいかわらず低迷したままで、ギリシャをはじめユーローの格差などさらにぎくしゃくし、加えてリーマンショックが追い討ちをかけています。しかし欧州の街並みは相変わらず美しく豊かに見えるのです。が、実際の彼らの生活はと言うと、その見かけとは裏腹にあまり楽とはいえません。特に旧ソビエト崩壊後の東欧旧社会主義国家の生活は苦しいもので、依然としてインフレ状況が続いているのです。
そんな状態にもかかわらず、私たち日本の旅行者には彼らの暮らしは、豊かでよく見えます。いったいどうしたと言うのでしょう?その原因があの数世紀にもわたる伝統的で堅固な住まいと、綺麗に揃った街並みにあることです。家の壁はレンガや石で積まれ分厚く重厚で、さらに南に下がって開放的なラテン系の国民の人柄や奔放な生き方や住まい方は変わっても、なぜかその家や街並みの様子はあまり変わらないのです。
彼らがかつて開拓したもっと多湿な南方や、アメリカなどの新大陸に渡って築いた植民地時代の家や街並みも材料は木材になってもその形態はほぼ同じなのです。その答えこそ彼らの長年に培われた“文化”で、彼らが長年に渡って築いてきた都市や家に暮らす本質的な文化のなせる技なのです。この“本質的な文化”とは、模倣されたそれとは違って、実はすべて必要に迫られたものばかりだったのです。われわれがイメージする彼らの家は決して豪華で明るいものではなく、すべて城壁の中にあって侵略に備えた街と家の形はそこに住む住民の使命であり、また時の統治者の厳しい義務でもあったのです。
地続きの大陸にあっていつ攻められ侵略されるか分からない城である街と、家は彼らにとっていわば「命」を守ることそのものなのです。同時にヨーロッパの主要都市は比較的緯度の高いところに発展したものが多く厳冬で、分厚い「壁の家」でないと凍えて死しんでしまうのです。分厚い壁と小さな窓は即、「命」がテーマとも言えるのです。
しかも次第に城壁が無くなったり、街が発展し城壁の中に住めなくなればさらに堅牢にわが家を造る必要もあったのです。

「傘の家」の文化に「壁の家」が入り込んで


「傘の家」は壁ではなく、柱と屋根組みだけの家です。ここに強靭で柔軟な柱と梁による木組みと、美しい屋根の文化が発展するのです。それは千年にもおよぶわが国の家の形です。ここに突如異文化の「壁の家」が入り込んで、私たちの過ごしやすい伝統的な「傘の家」の文化を混乱させ、しかも統一感のないバラバラの無秩序な街並みと、風通しの悪い密集した都市となっているのです、しかも中途半端な所有権のマンションの林立ともなっているのです。憂慮すべきは、こうした開放的で中途半端な家づくりの中でいかに身を守り住まいを長持ちさせるか、と言うことがこれから重要な課題となるのです。
関連記事
- 老いの国・老いの時代・老いの生活の家づくり
- 家の消費税10%?はあまりにも高い!
- 予算“0”の「ソフト壁」
- 「エンプティネスト」は災害に弱い
- 二世帯住宅は「同居“共働”住宅」?にする
- 秘伝!収納にも間取りと動線があるのです
- 老後に強い家はどうつくり、どうリフォームするか?
- 防犯と災害に強い「向こう三軒両隣」
- 六十歳で家を建てる!?“減築”して狭楽しく
- エコとはいったい何?節電で本当のエコを知る!
- レンガや石積みの家は身を守る家?~冷暖房の時代も「夏を旨とする」!
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

 注文住宅のハウスネットギャラリー
注文住宅のハウスネットギャラリー